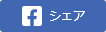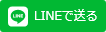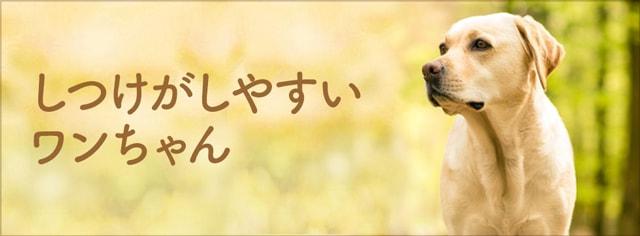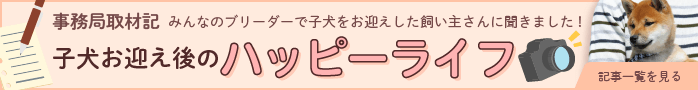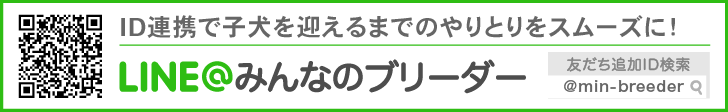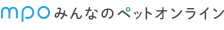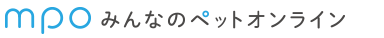犬の爪切りは必要? 頻度は?

犬の爪は人間と同じように放っておくとどんどん伸びていくので、定期的な爪切りが必要です。とくに犬の親指にあたる狼爪(5本目の爪)がある場合、地面につかないので散歩などで削れることがありません。飼い主さんがこまめにチェックしてあげましょう。
犬の爪切りが必要な理由
そもそも、なぜ犬の爪は伸ばしたままにしておいてはいけないのでしょうか。実は、爪が長いと次のような事態を招く危険性があります。
肉球を傷つけてしまう
犬の爪を放置したままにしておくとカーブ状に伸びていきます。そうすると肉球を傷つけたり、場合によっては刺さったりすることも。肉球が炎症を起こすと化膿して立てなくなってしまうこともあるので危険です。
うまく歩けなくなる恐れがある
犬は肉球を地面に着けて歩きますが、爪が長いと肉球ではなく爪が地面に着いてしまいます。それによって正しい歩様姿勢が取れず、関節を痛めてしまうなど、日常生活に支障が出る可能性があります。
爪が折れたり割れたりする
爪が地面に着いたまま動き回っていると、爪が割れたり折れたりすることも。犬にとても痛い思いをさせてしまいます。さらに、その経験がトラウマになり、爪を触られるだけで嫌がるようになるケースも少なくありません。
犬や飼い主がケガをするリスクがある
犬の爪が伸びたままだと、ほかの犬とじゃれた際に傷をつけてしまう可能性が高くなります。また、犬を抱っこした拍子に飼い主の腕に傷がつくことも。とくに小さい子どもがいる家庭では、犬に悪気がなくても子どもにケガを負わせてしまう危険があります。
上記の理由のほかに、伸びた爪が床やソファーなどの家具を傷付けてしまうことがあります。家具や床を守るためにも爪切りは有効です。
上記の理由のほかに、伸びた爪が床やソファーなどの家具を傷付けてしまうことがあります。家具や床を守るためにも爪切りは有効です。
犬の爪切りは月に1回を目安に
室内で生活して屋外での運動量が少ない犬は爪が伸びやすいなど、個体差や生活環境にもよりますが、犬の爪切りは月1回程度を目安に考えるようにしましょう。
1カ月を待たずとも、フローリングなどで動くときに爪が床に当たってカチャカチャと音を立てているようであれば爪が伸びているサインです。
また、爪が白っぽい色の場合、ピンク色に見える部分が血管です。爪を切らずに放置しておくと、血管も伸びてしまい、短くできなくなるので注意しましょう。
また、老犬など寝たきりになってしまった犬の場合は、犬の足を自分の手のひらに当ててみましょう。肉球よりも爪が当たるようであれば、爪切りが必要なサインです。
1カ月を待たずとも、フローリングなどで動くときに爪が床に当たってカチャカチャと音を立てているようであれば爪が伸びているサインです。
また、爪が白っぽい色の場合、ピンク色に見える部分が血管です。爪を切らずに放置しておくと、血管も伸びてしまい、短くできなくなるので注意しましょう。
また、老犬など寝たきりになってしまった犬の場合は、犬の足を自分の手のひらに当ててみましょう。肉球よりも爪が当たるようであれば、爪切りが必要なサインです。
犬の爪切りのやり方3ステップ

では次に、失敗しないで犬の爪を切るための3ステップを紹介します。
準備物
- 犬専用の爪切り
- やすり
- 止血剤
- ティッシュや布
犬の爪切りをする場合は、以上のアイテムを用意しましょう。とくに犬の爪は、人間の爪より硬く、人間用の爪切りで無理矢理切ろうとすると割れたり、折れたりするので、必ず専用のものを用意してください。
ギロチンタイプやニッパータイプのどちらでも大丈夫ですが、ギロチンタイプのほうが比較的、力を入れずに切りやすいでしょう。
犬の爪きりステップ1.保定(固定)する
爪を切ろうとしているときに犬が暴れてしまうとトラブルの原因になるため、まずは、犬の保定(固定)をします。床ではなく、腰の高さほどの机や台の上でおこなうとやりやすいでしょう。
※保定/動物の治療やお世話をする際に、動かないようにおさえておくこと
※保定/動物の治療やお世話をする際に、動かないようにおさえておくこと
保定の仕方
- 犬を立たせる
- 犬の体と垂直になるようにお尻側に向かって立つ
- 腕を犬の胴体に回し、自分の体の脇に引き寄せる
保定は爪を切りやすいように犬の体を固定することだけではなく、切っている様子を犬から見えなくする意味でも大切です。

犬の爪切りステップ2.爪を切る
愛犬の足を持ち、爪切りでカットします。このとき、犬が嫌がらなければ爪の根元を支えるイメージで軽く肉球を押しながら切ると、安定感が増して切りやすくなります。また、足は高く持ち上げすぎないように注意してください。
爪切りは、爪の根本と水平になるように持つようにしましょう。
切るのは、血管のない先端部分のみ。透かして見て血管の場所が分かる場合は確認して切り、黒っぽい爪で透かしても分からない場合は注意しながら少しずつ切っていきます。
血管ギリギリでカットすると、出血することが多いので、血管から2~3mmほど残して切るとよいでしょう。
黒爪の場合、切断面が白から透明っぽい色に変わるタイミングで切るのをやめると出血せずに切れますよ。
爪切りは、爪の根本と水平になるように持つようにしましょう。
切るのは、血管のない先端部分のみ。透かして見て血管の場所が分かる場合は確認して切り、黒っぽい爪で透かしても分からない場合は注意しながら少しずつ切っていきます。
血管ギリギリでカットすると、出血することが多いので、血管から2~3mmほど残して切るとよいでしょう。
黒爪の場合、切断面が白から透明っぽい色に変わるタイミングで切るのをやめると出血せずに切れますよ。


黒爪の血管の位置を把握するコツ
原田 友紀先生
爪の黒い子の場合は、断面が半透明になり、ザラザラの乾燥した感触からしっとりした状態に変わった、切った感触がやわらかいものになったと感じられるようになったら、血管が近いので切るのを止めましょう。
犬の爪切りステップ3.やすりで整える
切りっぱなしだと角が残っていたり、表面がザラザラしていたりします。そのままにしておくと犬が体を掻いたときなどにケガをして痛い思いをするので、やすりを使って角取りをしましょう。
このとき、切った面を削ってしまうと出血する可能性があるので、切った面は削らないように注意してください。
このとき、切った面を削ってしまうと出血する可能性があるので、切った面は削らないように注意してください。
犬が爪切りを嫌がる場合の対処法

一度でも爪切りが嫌な思い出になってしまうと今後ますます爪のケアがしづらくなります。無理に抑え込んだりするのではなく、下記のような方法でなるべく犬も楽しく爪切りができるように工夫しましょう。
スキンシップの延長でおこなう
多くの犬がいきなり足を触られることを嫌がります。普段のスキンシップの延長のように、最初は愛犬の喜ぶところからさわり、次に全身を触り、徐々に足に近づいていくようにしましょう。
たくさんほめる
爪を切るたびにほめたり、おやつをあげたりして、爪切りが嫌なことではないと印象づけると、今後も爪切りをしやすくなります。
二人でやる
一人がおやつなどで気を引きつつ、もう一人が爪切りをしてみる、もしくは一人が体を軽く固定をしつつもう一人が爪を切るなど、二人でおこなうとスムーズにできるでしょう。
大型犬など一人での保定が難しい場合などにもおすすめです。
大型犬など一人での保定が難しい場合などにもおすすめです。
口輪を使う
甘噛みなどでけん制してくる場合、口輪を使う方法もあります。口輪はきちんと犬のサイズに合ったものを選びましょう。大きすぎると犬が自分で外せてしまい、意味がなくなってしまいます。
無理せずプロに任せる
無理に自宅でおこない失敗してしまうと、爪切りがトラウマになるだけでなく、飼い主さんとの信頼関係に支障が出る可能性があります。嫌がる場合は無理をせずに動物病院やトリミングサロンへ相談しましょう。

爪切りは”慣らす”ことが大切
原田 友紀先生
いきなり爪を切るのではなく、足に触ってご褒美を与え、まずは「足を触られるとよいことがある」と覚えてもらい、足先を触られることに抵抗がなくなったら爪切りをおこないます。
また、嫌がる場合は1度に全部の爪切りをおこなうのではなく、1日1本切れたらOKにし、徐々に慣れてもらうと、よりお家でケアしやすくなります。
無理やりするとトラウマになるため、犬が嫌がったら無理に決行せず、様子を見ながら少しずつ切るのがおすすめです。
まずは、1日1本からはじめてみましょう。
また、嫌がる場合は1度に全部の爪切りをおこなうのではなく、1日1本切れたらOKにし、徐々に慣れてもらうと、よりお家でケアしやすくなります。
無理やりするとトラウマになるため、犬が嫌がったら無理に決行せず、様子を見ながら少しずつ切るのがおすすめです。
まずは、1日1本からはじめてみましょう。
獣医師に聞いた! 爪切りについてのQ&A

爪切りをしていたとき、出血してしまったらどうしたらいい?
清潔なティッシュやガーゼを2~3回折ったものを出血部位に当てて3分程やさしく圧迫してください。嫌がる場合はおやつなどで気を逸らしながら圧迫し、それでも出血が続いている場合は、小麦粉を出血部位が白く覆われる程度に塗って、その上からティッシュやガーゼで圧迫してください。 それでも出血が続く場合は凝固異常などの可能性があるので病院に行きましょう。
また、小麦粉は、小麦アレルギーの傾向がある子には使えない可能性もあります。
また、小麦粉は、小麦アレルギーの傾向がある子には使えない可能性もあります。
散歩をしていても、爪切りは必要?
24時間アスファルトや地面で削れているわけではなく、室内飼いが主流になってきている今、お散歩に行くだけでは削られきれない場合がほとんどです。とくに狼爪(ろうそう)は地面には着かないため、散歩に行っていても削れずに、気付いたときには巻き爪になっていたということがあります。
また、歩き方の癖によっては、一部の爪だけが削れ、一部が削れていないということもあるため、定期的にチェックをし、爪切りをおこなってあげた方が安心です。
また、歩き方の癖によっては、一部の爪だけが削れ、一部が削れていないということもあるため、定期的にチェックをし、爪切りをおこなってあげた方が安心です。
黒い爪の爪切りが怖いです。どうしたらいい?
黒い爪は慣れないうちは切りづらいかと思うので、一度病院やトリミングでやり方を見せてもらい、家で1本ずつ練習するのがいいかと思います。
実際に獣医師やトリマーの前で一度自分で切ってみると、切る感覚が身に付きますので、爪切りを教えてもらえないかと聞いてみるのもひとつです。 それでも怖いという場合は、無理せずプロに任せるか、こまめにやすりを使って削るようにしましょう。
実際に獣医師やトリマーの前で一度自分で切ってみると、切る感覚が身に付きますので、爪切りを教えてもらえないかと聞いてみるのもひとつです。 それでも怖いという場合は、無理せずプロに任せるか、こまめにやすりを使って削るようにしましょう。
爪切りだけで病院に行ってもいい?
爪切りのみで病院に来られる方はたくさんいらっしゃいます。「こんなことで病院なんて……」とは思わず、お気軽にお越しください。
料金は病院によって異なりますが、大体500円前後のところが多いかと思います。プラスで再診料もかかるところがございますので、詳細はかかりつけ病院にお問い合わせください。
料金は病院によって異なりますが、大体500円前後のところが多いかと思います。プラスで再診料もかかるところがございますので、詳細はかかりつけ病院にお問い合わせください。
獣医師からのメッセージ
「爪切り=楽しい時間」とワンちゃんに覚えてもらうことが楽に爪切りをおこなうための第一歩です。
一度痛みを経験してしまうとトラウマになり、足先を触っただけでパニックになってしまうこともあるので、まずは正しいやり方を身に付けることが大切です。
慣れるまでは病院やトリミングで切ってもらっても大丈夫なので、焦らず少しずつ進めていきましょう。
一度痛みを経験してしまうとトラウマになり、足先を触っただけでパニックになってしまうこともあるので、まずは正しいやり方を身に付けることが大切です。
慣れるまでは病院やトリミングで切ってもらっても大丈夫なので、焦らず少しずつ進めていきましょう。
まとめ

身だしなみとしてだけではなく、健康を保持するためにも重要な爪のケアですが、せっかく自宅でおこなうなら、飼い主さんとのコミュニケーションの一環としてやりたいですね。お手入れもでき、絆も深まり一石二鳥です。また、普段はプロに頼んでいる人も災害時などいざというときのために爪切りトレーニングをしておくと安心でしょう。爪切りグッズもペット用災害グッズのひとつとして備えておいてくださいね。