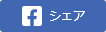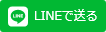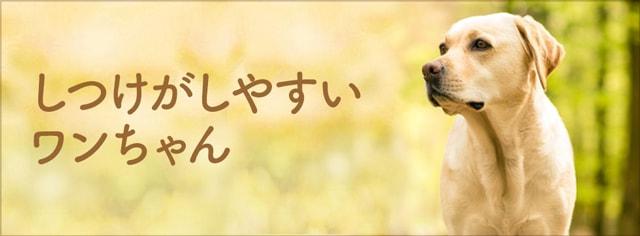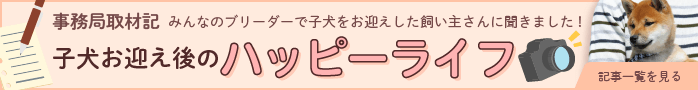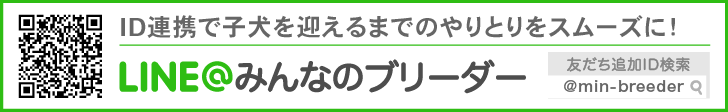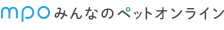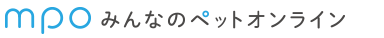愛犬にマダニを見つけても取っちゃダメ!

吸血ダニの一種、マダニは、3~8mmと目視で確認できるサイズで、さらに吸血後は1~2cmに膨れあがるため、比較的発見しやすいダニといえます。
また、湿っぽく被毛の少ない部位を好むため、愛犬の血を今まさに吸血中というマダニを見つけることがあるかもしれません。
しかしその場合、手で取ったり、潰してしまったりしないよう気を付けましょう。
マダニはハサミのような口で皮膚に噛みつきセメントのような物質で固着して吸血するため、無理に取ると胴体が切れ、頭部や口が皮膚中に残ってしまいます。
また、マダニが病原体を持っている可能性を考え、マダニを指でつまんだり、潰したりすることは絶対にしないでください。
指で圧迫されたマダニから病原体が体内に逆流したり、潰したマダニの体液が刺入部位から侵入し病原体に感染したり、化膿してしまうおそれがあります。
専用のピンセットを使用するか、または、病院で取り除いてもらいましょう。
また、湿っぽく被毛の少ない部位を好むため、愛犬の血を今まさに吸血中というマダニを見つけることがあるかもしれません。
しかしその場合、手で取ったり、潰してしまったりしないよう気を付けましょう。
マダニはハサミのような口で皮膚に噛みつきセメントのような物質で固着して吸血するため、無理に取ると胴体が切れ、頭部や口が皮膚中に残ってしまいます。
また、マダニが病原体を持っている可能性を考え、マダニを指でつまんだり、潰したりすることは絶対にしないでください。
指で圧迫されたマダニから病原体が体内に逆流したり、潰したマダニの体液が刺入部位から侵入し病原体に感染したり、化膿してしまうおそれがあります。
専用のピンセットを使用するか、または、病院で取り除いてもらいましょう。
マダニとは

ダニは昆虫のようですが、実は8本脚をもつ節足動物で、クモの仲間です。
大きさは吸血前のものでも3~8mmあり、肉眼で確認できるダニです。
栄養源は人や犬をはじめとする哺乳動物の血で、発育、脱皮、産卵のために吸血します。
まぶた、耳、鼻まわり、首輪の下、内股、指の間など、被毛が少なくて、皮膚が薄い、湿気がこもる部位に寄生されやすいです。
宿主の皮膚に口器を突き刺して吸血するのですが、マダニの唾液には麻酔のような効果のある物質が含まれており、人が寄生された場合は噛まれたことに気付かないケースもあるといわれています。
体の小さい動物、小型犬などの場合は、多数寄生されると吸血により貧血になることもあるため、注意が必要です。
マダニは森や山だけでなく、公園の草むらや河川敷などあらゆるところに生息し、春から秋にかけて活動が盛んになり、気温が低下する冬の間も活動するといわれています。
そのため屋外では、自然豊かなキャンプ場やドッグラン、緑の多い散歩コースなどは危険といえます。なるべく草むらに入らないよう気を付けましょう。
大きさは吸血前のものでも3~8mmあり、肉眼で確認できるダニです。
栄養源は人や犬をはじめとする哺乳動物の血で、発育、脱皮、産卵のために吸血します。
まぶた、耳、鼻まわり、首輪の下、内股、指の間など、被毛が少なくて、皮膚が薄い、湿気がこもる部位に寄生されやすいです。
宿主の皮膚に口器を突き刺して吸血するのですが、マダニの唾液には麻酔のような効果のある物質が含まれており、人が寄生された場合は噛まれたことに気付かないケースもあるといわれています。
体の小さい動物、小型犬などの場合は、多数寄生されると吸血により貧血になることもあるため、注意が必要です。
マダニは森や山だけでなく、公園の草むらや河川敷などあらゆるところに生息し、春から秋にかけて活動が盛んになり、気温が低下する冬の間も活動するといわれています。
そのため屋外では、自然豊かなキャンプ場やドッグラン、緑の多い散歩コースなどは危険といえます。なるべく草むらに入らないよう気を付けましょう。

マダニを見つけても慌てず病院へ
原田 友紀先生
もしも、わんちゃんの皮膚にマダニを見つけても、慌てて取ろうとせずにまずは動物病院へ連れていきましょう。マダニは口器を皮膚に刺してセメント様の物質で固定しているので、取り残す可能性があります。
また、マダニはわんちゃんに重度の貧血を引き起こすバベシアや、人間にも重篤な症状を引き起こすSFTSウイルスを保有している危険性があるため、感染症予防の面からも必ず獣医師に相談してください。
万が一、飼い主さまもマダニに咬まれてしまった場合は、人の医療機関を受診ください。
また、マダニはわんちゃんに重度の貧血を引き起こすバベシアや、人間にも重篤な症状を引き起こすSFTSウイルスを保有している危険性があるため、感染症予防の面からも必ず獣医師に相談してください。
万が一、飼い主さまもマダニに咬まれてしまった場合は、人の医療機関を受診ください。
犬に寄生するダニはほかにも

ヒゼンダニ
イヌミミヒゼンダニ
イヌミミヒゼンダニは犬の耳の外耳道(耳の入り口~鼓膜の手前)に寄生するダニで、耳ダニ、耳疥癬(みみかいせん)とも呼ばれています。
大きさは0.3~0.5mmほどで肉眼では確認できません。
犬の耳の皮膚表面に寄生し、耳垢や皮膚、分泌物を食べて繁殖します。
寄生されると大量の黒っぽい耳垢が出ますが、これはミミヒゼンダニの糞です。
感染している犬との接触やミミヒゼンダニの成虫や卵を含んだ耳垢に汚染されたタオルやベッドなどから感染します。
寄生されている犬はかゆみのせいで耳を搔いたり頭を振ったりすることがあります。
また、耳が臭う、耳のあたりを触られることを嫌がるなどの症状が見られ、なかには耳血腫(耳介が内出血で膨らんでしまう病気)を併発することも。
大きさは0.3~0.5mmほどで肉眼では確認できません。
犬の耳の皮膚表面に寄生し、耳垢や皮膚、分泌物を食べて繁殖します。
寄生されると大量の黒っぽい耳垢が出ますが、これはミミヒゼンダニの糞です。
感染している犬との接触やミミヒゼンダニの成虫や卵を含んだ耳垢に汚染されたタオルやベッドなどから感染します。
寄生されている犬はかゆみのせいで耳を搔いたり頭を振ったりすることがあります。
また、耳が臭う、耳のあたりを触られることを嫌がるなどの症状が見られ、なかには耳血腫(耳介が内出血で膨らんでしまう病気)を併発することも。
イヌセンコウヒゼンダニ
イヌセンコウヒゼンダニは犬の皮膚上に寄生し、皮膚にトンネルを作ります。
サイズは0.2~0.4mmと小さく、肉眼では確認できません。
寄生されると疥癬(かいせん)という伝染性の皮膚感染症を引き起こします。
皮膚トンネル内の糞や分泌物が原因となり、発疹と強いかゆみが出ます。
体には掻き傷や脱毛が増え、さらに進行するとかさぶたやフケが大量に出ます。
ヒゼンダニは毛のない皮膚を好むため、犬の耳、肘、おなか、かかとでの赤み、フケ、脱毛などの症状から始まり、さらに進行すると引っ掻き傷やかさぶたがみられます。
炎症は体の広い範囲に広がりますが、肉眼ではダニが見えないため、アトピー性皮膚炎と間違われるケースもあるようです。
イヌセンコウヒゼンダニの感染と疥癬発症の原因の多くは、すでに感染している動物との接触だけではなく、感染動物に使用したブラシやタオル、ベッド類からも感染します。
犬から犬へ、ときには人へも感染するため注意が必要です。
多くの犬が利用するペットショップやドッグラン、トリミングサロンなどは感染のリスクが高いといえるでしょう。
サイズは0.2~0.4mmと小さく、肉眼では確認できません。
寄生されると疥癬(かいせん)という伝染性の皮膚感染症を引き起こします。
皮膚トンネル内の糞や分泌物が原因となり、発疹と強いかゆみが出ます。
体には掻き傷や脱毛が増え、さらに進行するとかさぶたやフケが大量に出ます。
ヒゼンダニは毛のない皮膚を好むため、犬の耳、肘、おなか、かかとでの赤み、フケ、脱毛などの症状から始まり、さらに進行すると引っ掻き傷やかさぶたがみられます。
炎症は体の広い範囲に広がりますが、肉眼ではダニが見えないため、アトピー性皮膚炎と間違われるケースもあるようです。
イヌセンコウヒゼンダニの感染と疥癬発症の原因の多くは、すでに感染している動物との接触だけではなく、感染動物に使用したブラシやタオル、ベッド類からも感染します。
犬から犬へ、ときには人へも感染するため注意が必要です。
多くの犬が利用するペットショップやドッグラン、トリミングサロンなどは感染のリスクが高いといえるでしょう。
予防法
イヌミミヒゼンダニとイヌセンコウヒゼンダニは、感染した犬との接触が主な感染経路です。
直接接触しなくても、感染した犬が体や頭を振った際にダニが飛び散ったり、感染した犬に使用したブラシやタオル、ベッドなどのグッズを使ったりしたことで、感染したというケースもあります。
どちらのヒゼンダニも、宿主の体から離れてもしばらくは生きることができます。仮に振り落とされ下へ落ちても、次の宿主へ移ることは難しくありません。
予防法としては
があげられます。
直接接触しなくても、感染した犬が体や頭を振った際にダニが飛び散ったり、感染した犬に使用したブラシやタオル、ベッドなどのグッズを使ったりしたことで、感染したというケースもあります。
どちらのヒゼンダニも、宿主の体から離れてもしばらくは生きることができます。仮に振り落とされ下へ落ちても、次の宿主へ移ることは難しくありません。
予防法としては
- 他の犬との接触やたくさんの犬が利用する施設を訪れる際には注意する
- 生活スペースを清潔に保つ(フケや耳垢からの再感染予防)
- 定期的なシャンプーや耳掃除をして早期発見に努める
があげられます。
ニキビダニ
ニキビダニは皮膚の毛包(毛穴)内に常在しているダニで、毛包虫やアカラスと呼ぶこともあります。
サイズは0.3mm前後と大変小さく、肉眼では確認できません。
宿主が健康な状態であれば悪さをしませんが、皮膚のバリア機能低下や免疫力低下、遺伝的な要因などが原因となり、皮膚炎を起こすことがあります。
子犬の感染であれば未熟な免疫機能や環境の変化、シニア犬であれば老化に伴う免疫力低下やホルモン失調などがきっかけになるようです。
発症初期にはかゆみの症状はなく、目と口の周辺、顔面、四肢の先などに脱毛の症状だけがみられます。
重症化すると全身へ広がり、二次感染を起こすと強いかゆみも引き起こします。
サイズは0.3mm前後と大変小さく、肉眼では確認できません。
宿主が健康な状態であれば悪さをしませんが、皮膚のバリア機能低下や免疫力低下、遺伝的な要因などが原因となり、皮膚炎を起こすことがあります。
子犬の感染であれば未熟な免疫機能や環境の変化、シニア犬であれば老化に伴う免疫力低下やホルモン失調などがきっかけになるようです。
発症初期にはかゆみの症状はなく、目と口の周辺、顔面、四肢の先などに脱毛の症状だけがみられます。
重症化すると全身へ広がり、二次感染を起こすと強いかゆみも引き起こします。
予防法
ニキビダニは健康な犬にも普段から毛包内にいるダニで、体調不良や免疫力低下、発情や妊娠、ストレスなどが原因で増殖します。
生後2~3日で母犬から感染するとされており、成犬同士の接触で感染することはありません。また、特定の種類の生物のみを宿主とする性質「宿主特異性」が高いダニで、犬から人に感染することはほとんどないとされています。
免疫力の低下が発症の要因の一つとされているため、ストレスを与えず、生活スペースを清潔に保つことが予防に有効です。
生後2~3日で母犬から感染するとされており、成犬同士の接触で感染することはありません。また、特定の種類の生物のみを宿主とする性質「宿主特異性」が高いダニで、犬から人に感染することはほとんどないとされています。
免疫力の低下が発症の要因の一つとされているため、ストレスを与えず、生活スペースを清潔に保つことが予防に有効です。
マダニが媒介する病気

病原体を保有しているダニから感染する病気を「ダニ媒介感染症」といいます。
ここでは、代表的な3つのダニ媒介感染症について説明します。
ここでは、代表的な3つのダニ媒介感染症について説明します。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
重症熱性血小板減少症候群は主に、ウィルスを保有しているマダニに咬まれることにより感染します。
発熱、嘔吐、下痢などの消化器症状のほかに、血小板減少や白血球減少といった症状がみられます。
重症化すると命にかかわることもあり、致死率は人・犬ともに10~30%ほど、猫については60%にいたる、比較的致死率の高い病気です。
現在までに有効な治療薬はみつかっていません。
人も犬もかかる人獣共通感染症(ズーノーシス)のひとつで、通常はマダニを介して感染する病気です。ですが、感染動物および感染者の血液や体液、尿や便などの排泄物との接触感染や感染動物に咬まれたことによる感染も報告されています。
発熱、嘔吐、下痢などの消化器症状のほかに、血小板減少や白血球減少といった症状がみられます。
重症化すると命にかかわることもあり、致死率は人・犬ともに10~30%ほど、猫については60%にいたる、比較的致死率の高い病気です。
現在までに有効な治療薬はみつかっていません。
人も犬もかかる人獣共通感染症(ズーノーシス)のひとつで、通常はマダニを介して感染する病気です。ですが、感染動物および感染者の血液や体液、尿や便などの排泄物との接触感染や感染動物に咬まれたことによる感染も報告されています。
ライム病
マダニが保有するボレリアという細菌が引き起こす、SFTSと同じ人獣共通感染症のひとつで、マダニに吸血されることで感染します。
犬が感染しても症状がみられることはまれですが、急性症状として食欲不振や起立不能、発熱がみられます。
また、関節炎を引き起こし、関節の痛みによる脚をかばって歩いたり、引きずったりして歩く「跛行(はこう)」がみられるケースもあります。
急性腎不全や糸球体腎炎がみられることもあります。
人ではマダニに吸血された部位を中心として特徴的な遊走性紅斑がみられます。
犬が感染しても症状がみられることはまれですが、急性症状として食欲不振や起立不能、発熱がみられます。
また、関節炎を引き起こし、関節の痛みによる脚をかばって歩いたり、引きずったりして歩く「跛行(はこう)」がみられるケースもあります。
急性腎不全や糸球体腎炎がみられることもあります。
人ではマダニに吸血された部位を中心として特徴的な遊走性紅斑がみられます。
バベシア症
バベシア症はバベシア原虫を保有するマダニに咬まれることで感染します。
バベシアは赤血球に寄生し、増殖した時に赤血球が壊されるため、溶血性貧血と発熱が起こります。
貧血が進むにつれて歯茎などの可視粘膜の色が白くなり、食欲不振や起立困難などがみられます。
破壊された赤血球の色素によって尿が赤くなったり(血色素尿)、黄疸や脾腫なども起こります。重症化すればDIC(播種性血管内凝固症候群)や多臓器不全を起こすため、治療が遅れると命にかかわる場合も。
一方で感染しても症状が表れないケースもあり、これを不顕性(ふけんせい)感染といいます。
また、一度感染すると完治が難しく、症状がみられなくなったあとでもキャリア(不顕性持続感染)となり、免疫力低下やストレス、免疫抑制剤の投与、脾臓摘出手術などが原因で再発することも少なくありません。
これは不顕性感染の場合も同じで、注意が必要です。
マダニに咬まれることだけでなく、出血を伴うケンカや輸血などから感染することもあります。
犬から人への感染はありません。
バベシアは赤血球に寄生し、増殖した時に赤血球が壊されるため、溶血性貧血と発熱が起こります。
貧血が進むにつれて歯茎などの可視粘膜の色が白くなり、食欲不振や起立困難などがみられます。
破壊された赤血球の色素によって尿が赤くなったり(血色素尿)、黄疸や脾腫なども起こります。重症化すればDIC(播種性血管内凝固症候群)や多臓器不全を起こすため、治療が遅れると命にかかわる場合も。
一方で感染しても症状が表れないケースもあり、これを不顕性(ふけんせい)感染といいます。
また、一度感染すると完治が難しく、症状がみられなくなったあとでもキャリア(不顕性持続感染)となり、免疫力低下やストレス、免疫抑制剤の投与、脾臓摘出手術などが原因で再発することも少なくありません。
これは不顕性感染の場合も同じで、注意が必要です。
マダニに咬まれることだけでなく、出血を伴うケンカや輸血などから感染することもあります。
犬から人への感染はありません。

日ごろのマダニ予防が大切
原田 友紀先生
ダニ媒介性感染症のひとつであるバベシア症は、重度の溶血性貧血を起こすため、1割程度のわんちゃんが亡くなる可能性があります。動物病院には人間のような血液のストックもなければ、献血制度もありません。いざ輸血が必要な時にすぐに血液が用意できないことは命に関わってきます。
また、犬専用のバベシア治療薬はないため牛用の薬を使用したり、抗原虫作用のある抗生物質を長期的に飲ませる必要があります。苦労して治療をして回復したとしても、完全に体内からバベシアを駆除する事は難しいため、再発の恐れが常につきまといます。
マダニから犬の体内へバベシアが移ってくるのは、吸血開始から48時間以降です。マダニの予防薬をきちんとしていれば48時間以内に駆除が可能なので、欠かさずに予防しましょう。もしマダニを発見したら速やかに動物病院へ連れて行ってください。
重症熱性血小板減少症候群は2013年に国内ではじめて感染報告されましたが、現在の獣医学では有効な治療法もワクチンもなく、3割程度のわんちゃんが亡くなっています。
発熱や嘔吐、下痢などのありふれた症状が主で、黄疸や血小板減少、白血球減少などもみられますが、対症療法をしながら回復を祈るしかありません。
原因となるSFTSウイルスは発症動物の血液、体液、排泄物などにも含まれており、それらから人へ感染した報告もあるため注意が必要です。遺体から感染した報告もあるので、野良猫や野生動物の遺体にはわんちゃんを近づけたり、素手で触ったりしないでください。
残念ながら定期的なマダニ予防をしていてもSFTSウイルスに感染したという報告があります。しかし、有効な治療法がないのでマダニに咬まれないようにすることが現時点でできるもっとも有効な予防です。定期的なマダニ予防を欠かさないだけでなく、草むらにはなるべく入らない、散歩から帰ったらブラッシングをして吸血前のマダニを落とすことも忘れないようにしましょう。
また、犬専用のバベシア治療薬はないため牛用の薬を使用したり、抗原虫作用のある抗生物質を長期的に飲ませる必要があります。苦労して治療をして回復したとしても、完全に体内からバベシアを駆除する事は難しいため、再発の恐れが常につきまといます。
マダニから犬の体内へバベシアが移ってくるのは、吸血開始から48時間以降です。マダニの予防薬をきちんとしていれば48時間以内に駆除が可能なので、欠かさずに予防しましょう。もしマダニを発見したら速やかに動物病院へ連れて行ってください。
重症熱性血小板減少症候群は2013年に国内ではじめて感染報告されましたが、現在の獣医学では有効な治療法もワクチンもなく、3割程度のわんちゃんが亡くなっています。
発熱や嘔吐、下痢などのありふれた症状が主で、黄疸や血小板減少、白血球減少などもみられますが、対症療法をしながら回復を祈るしかありません。
原因となるSFTSウイルスは発症動物の血液、体液、排泄物などにも含まれており、それらから人へ感染した報告もあるため注意が必要です。遺体から感染した報告もあるので、野良猫や野生動物の遺体にはわんちゃんを近づけたり、素手で触ったりしないでください。
残念ながら定期的なマダニ予防をしていてもSFTSウイルスに感染したという報告があります。しかし、有効な治療法がないのでマダニに咬まれないようにすることが現時点でできるもっとも有効な予防です。定期的なマダニ予防を欠かさないだけでなく、草むらにはなるべく入らない、散歩から帰ったらブラッシングをして吸血前のマダニを落とすことも忘れないようにしましょう。
マダニの感染経路

マダニは屋外の草木が生えるあらゆる場所に生息しています。
植物の葉の先や裏、茎の先端、落ち葉の中などに身を潜め、宿主が現れるのを待ち、動物の体温体臭、や吐き出す二酸化炭素や物理的振動などを感知したら飛び移ります。
家族が服やカバンなどについたマダニを知らずに持ち帰り、自宅で犬に感染するケースもあります。
植物の葉の先や裏、茎の先端、落ち葉の中などに身を潜め、宿主が現れるのを待ち、動物の体温体臭、や吐き出す二酸化炭素や物理的振動などを感知したら飛び移ります。
家族が服やカバンなどについたマダニを知らずに持ち帰り、自宅で犬に感染するケースもあります。
犬のマダニの予防法

最後に、具体的なマダニの予防法を紹介します。
マダニに寄生されないための効果的な方法は
などがあげられます。
市販されている虫よけ剤や首輪、虫よけシャンプーなどは予防効果が乏しいので、きちんと動物病院で処方された薬を使用しましょう。
予防薬にもなる駆除薬は、スポットタイプとチュアブルタイプがあり、どちらもダニ駆除専用のものとフィラリア予防を兼ねているものがあります。
獣医師と相談し、ワクチンスケジュールとともに、愛犬に適切な薬と服用期間を決めましょう。
マダニに寄生されないための効果的な方法は
- なるべく草むらに行かせない
- 服を着せる
- 毎日のブラッシングを心がける
- 散歩から帰ったらブラッシングする
- 毎日体を触ってチェックする(とくに耳や瞼などの顔、指の間も忘れずに)
- 1年を通してマダニ駆除薬を定期的・継続的に与える
などがあげられます。
市販されている虫よけ剤や首輪、虫よけシャンプーなどは予防効果が乏しいので、きちんと動物病院で処方された薬を使用しましょう。
予防薬にもなる駆除薬は、スポットタイプとチュアブルタイプがあり、どちらもダニ駆除専用のものとフィラリア予防を兼ねているものがあります。
獣医師と相談し、ワクチンスケジュールとともに、愛犬に適切な薬と服用期間を決めましょう。
スポット薬
液状の薬を、直接皮膚に滴下するタイプです。
投薬が難しいい犬や食物アレルギーがあるためチュアブル薬を服用できない犬にも有効です。
首の後ろに滴下してから全身にいきわたるまで24時間ほどかかります。万が一、犬が舐めてしまっても害はありませんが、一時的にヨダレが見られるので、犬が舐められないところに滴下してください。
滴下する前後数日はシャンプーを控えた方がよいでしょう。滴下した部分が数時間はベタベタするので、子どもが触らないように注意が必要です。
犬によっては皮膚が赤くなったり、脱毛したり、毛が変色することもあります。
体表面の薬剤に触れると吸血する前にマダニが逃げていく、忌避効果のあるスポット薬もあります。
使い切りで、1回でおおよそ1カ月間効果が持続します。
量は体重別になり、費用も犬のサイズによって異なり、小型犬用1回分1,500円前後、中型犬用1回分1,800円前後が目安です。
フィラリア予防効果もあるスポット薬は価格が異なりますので、正確な金額はかかりつけの病院にご確認ください。
投薬が難しいい犬や食物アレルギーがあるためチュアブル薬を服用できない犬にも有効です。
首の後ろに滴下してから全身にいきわたるまで24時間ほどかかります。万が一、犬が舐めてしまっても害はありませんが、一時的にヨダレが見られるので、犬が舐められないところに滴下してください。
滴下する前後数日はシャンプーを控えた方がよいでしょう。滴下した部分が数時間はベタベタするので、子どもが触らないように注意が必要です。
犬によっては皮膚が赤くなったり、脱毛したり、毛が変色することもあります。
体表面の薬剤に触れると吸血する前にマダニが逃げていく、忌避効果のあるスポット薬もあります。
使い切りで、1回でおおよそ1カ月間効果が持続します。
量は体重別になり、費用も犬のサイズによって異なり、小型犬用1回分1,500円前後、中型犬用1回分1,800円前後が目安です。
フィラリア予防効果もあるスポット薬は価格が異なりますので、正確な金額はかかりつけの病院にご確認ください。
チュアブル薬
チュアブルとはかみ砕いて服用する錠剤状の薬です。
食べやすいよう、ビーフ味やチキン風味など、犬の嗜好に合わせたものが主流となっています。
基本的には効果は1カ月ですが、3カ月効果が持続するものもあります。
フィラリア予防効果も含んだ薬は毎月投薬が必要です。
投薬してから4~8時間後には全身にいきわたり、体についているマダニを駆除することができますが、スポット薬と異なり、マダニが吸血しないと駆除できません。
内服薬であるため、まれに嘔吐や下痢などの消化器症状がみられることがあります。
また、使われている材料によってアレルギーを起こす可能性があるため、食物アレルギーのある犬に使用する際には必ずかかりつけ医にご相談ください。
費用の目安としては小型犬1カ月タイプ1回分1,600円前後、中型犬1カ月タイプ1回分1,900前後、小型犬3カ月タイプ1回分4,500円前後、中型犬3カ月タイプ1回分5,000円前後です。
こちらもフィラリア予防効果もあるチュアブル薬は価格が異なりますので、かかりつけの病院へお問い合わせください。
食べやすいよう、ビーフ味やチキン風味など、犬の嗜好に合わせたものが主流となっています。
基本的には効果は1カ月ですが、3カ月効果が持続するものもあります。
フィラリア予防効果も含んだ薬は毎月投薬が必要です。
投薬してから4~8時間後には全身にいきわたり、体についているマダニを駆除することができますが、スポット薬と異なり、マダニが吸血しないと駆除できません。
内服薬であるため、まれに嘔吐や下痢などの消化器症状がみられることがあります。
また、使われている材料によってアレルギーを起こす可能性があるため、食物アレルギーのある犬に使用する際には必ずかかりつけ医にご相談ください。
費用の目安としては小型犬1カ月タイプ1回分1,600円前後、中型犬1カ月タイプ1回分1,900前後、小型犬3カ月タイプ1回分4,500円前後、中型犬3カ月タイプ1回分5,000円前後です。
こちらもフィラリア予防効果もあるチュアブル薬は価格が異なりますので、かかりつけの病院へお問い合わせください。
獣医師Q&A
マダニは吸血が終わったら自然と犬から離れる? ついているのが1匹くらいなら、様子を見ても大丈夫?
マダニは満腹になるまで吸血すると自然に離れていきます。その期間は数日から、長い場合は10日ほどに及ぶこともあります。
しかしバベシア原虫はマダニが吸血し始めて2日後から犬の体内へ移りはじめます。SFTSウイルスにいたっては正確なことはまだ不明ですが、吸血開始から比較的早い段階で感染するのではないかと考えられています。
そのため、ダニ媒介性感染症に感染しないためにもマダニを発見した際には、たった1匹だけだとしても動物病院でできるだけ速やかに適切な処置を受けましょう。
しかしバベシア原虫はマダニが吸血し始めて2日後から犬の体内へ移りはじめます。SFTSウイルスにいたっては正確なことはまだ不明ですが、吸血開始から比較的早い段階で感染するのではないかと考えられています。
そのため、ダニ媒介性感染症に感染しないためにもマダニを発見した際には、たった1匹だけだとしても動物病院でできるだけ速やかに適切な処置を受けましょう。
スポット薬とチュアブル薬はどっちがいいの?
スポット薬がおすすめなのはお薬を飲むのが苦手な子、食物アレルギーがあってチュアブル薬が飲めない子、飲み薬でおなかを壊しやすい子などです。
スポット薬は吸血前にマダニが駆除できる可能性がありますが、体の先端部(足先、顔、尾など)は薬の濃度が低くマダニに狙われやすいので、こまめな全身チェックやブラッシングをしてあげましょう。
地域によってはスポット薬に耐性をもつマダニが生息しておりますので、かかりつけの先生ともご相談ください。
チュアブル薬がおすすめなのは食べることが大好きな子、頻繁にシャンプーをする子、小さなお子様と同居されている子、抱っこが好きな子です。
チュアブル薬は吸血しないとマダニが駆除できませんが、全身くまなく効果があって、駆除するスピードが早いことが特徴です。シャンプーや抱っこも気兼ねなくできますね。
食事と一緒に投与した方がよいいお薬もあるので、服用するタイミングは必ずかかりつけの先生に確認してください。
どちらのお薬がよいのかは、わんちゃんの性格や体質、生活スタイルに合わせて選択されるとよいでしょう。
スポット薬は吸血前にマダニが駆除できる可能性がありますが、体の先端部(足先、顔、尾など)は薬の濃度が低くマダニに狙われやすいので、こまめな全身チェックやブラッシングをしてあげましょう。
地域によってはスポット薬に耐性をもつマダニが生息しておりますので、かかりつけの先生ともご相談ください。
チュアブル薬がおすすめなのは食べることが大好きな子、頻繁にシャンプーをする子、小さなお子様と同居されている子、抱っこが好きな子です。
チュアブル薬は吸血しないとマダニが駆除できませんが、全身くまなく効果があって、駆除するスピードが早いことが特徴です。シャンプーや抱っこも気兼ねなくできますね。
食事と一緒に投与した方がよいいお薬もあるので、服用するタイミングは必ずかかりつけの先生に確認してください。
どちらのお薬がよいのかは、わんちゃんの性格や体質、生活スタイルに合わせて選択されるとよいでしょう。
獣医師からのメッセージ
マダニはわんちゃんや人に感染症をうつしてくる厄介な存在です。ここで紹介した感染症以外にも、多くの病原体を保有している危険性があります。
マダニは幼ダニ、若ダニ、成ダニと成長していく過程で2回吸血をして、3回目の吸血をした後に産卵します。幼ダニは1mm程度ととても小さく、若ダニでも2mmに満たない大きさです。成ダニも吸血前は3~4mmなので、わんちゃんの毛の中から見つける事はなかなか困難なため、マダニの予防薬が効果を発揮してくれます。
近年ではわんちゃんを連れてのお出かけも珍しくなくなりました。山間部のドッグランに遊びに行ったり、キャンプに出かけたり、大きな公園に一緒にお花見に行ったり、とても素敵な思い出になると思います。ですが、自然豊かな場所にはマダニもたくさん生息しています。また、そういった場所に出かけられたわんちゃんがマダニを持ち帰り、皆さんのご近所の公園や散歩コースに持ち込んでしまう危険性もあります。都市部だからといって油断は大敵です。
多くのダニ媒介性性感染症は西日本で猛威をふるっていますが、その脅威は徐々に北へと広がりつつあります。また、病原体をもつマダニは全国で確認されています。マダニは真冬の間もあたたかい落ち葉の中に身を潜め、春を待ちながらわんちゃんが通りかかるのをじっと待っています。暖かい季節だけではなく、1年中予防することを推奨します。
また、マダニは人にも危険な病原体を保有しているため、飼い主さんも草むらに入るときはなるべく肌を露出させないように長袖、長ズボンを着用したり、防ダニスプレーを併用するとよいでしょう。帰宅後は、自身の衣服や肌にマダニがついていないか確認しましょう。もしもマダニに咬まれてしまった場合は、自分で引っ張って取ることはせずに、医療機関で処置をしてもらいましょう。その後は医師の指示に従い、体調の変化には十分注意してください。
マダニについての正しい知識と対応方法を学んで、わんちゃんとのお出かけを安全に楽しんでいただければと思います。
マダニは幼ダニ、若ダニ、成ダニと成長していく過程で2回吸血をして、3回目の吸血をした後に産卵します。幼ダニは1mm程度ととても小さく、若ダニでも2mmに満たない大きさです。成ダニも吸血前は3~4mmなので、わんちゃんの毛の中から見つける事はなかなか困難なため、マダニの予防薬が効果を発揮してくれます。
近年ではわんちゃんを連れてのお出かけも珍しくなくなりました。山間部のドッグランに遊びに行ったり、キャンプに出かけたり、大きな公園に一緒にお花見に行ったり、とても素敵な思い出になると思います。ですが、自然豊かな場所にはマダニもたくさん生息しています。また、そういった場所に出かけられたわんちゃんがマダニを持ち帰り、皆さんのご近所の公園や散歩コースに持ち込んでしまう危険性もあります。都市部だからといって油断は大敵です。
多くのダニ媒介性性感染症は西日本で猛威をふるっていますが、その脅威は徐々に北へと広がりつつあります。また、病原体をもつマダニは全国で確認されています。マダニは真冬の間もあたたかい落ち葉の中に身を潜め、春を待ちながらわんちゃんが通りかかるのをじっと待っています。暖かい季節だけではなく、1年中予防することを推奨します。
また、マダニは人にも危険な病原体を保有しているため、飼い主さんも草むらに入るときはなるべく肌を露出させないように長袖、長ズボンを着用したり、防ダニスプレーを併用するとよいでしょう。帰宅後は、自身の衣服や肌にマダニがついていないか確認しましょう。もしもマダニに咬まれてしまった場合は、自分で引っ張って取ることはせずに、医療機関で処置をしてもらいましょう。その後は医師の指示に従い、体調の変化には十分注意してください。
マダニについての正しい知識と対応方法を学んで、わんちゃんとのお出かけを安全に楽しんでいただければと思います。
まとめ

ダニは多くの病原体をもち、ときには命にかかわる感染症を引き起します。
とくにマダニはあらゆるところに生息しているため、散歩のたびに寄生リスクがあるといえるでしょう。
しかし、駆除薬・予防薬、混合ワクチンの接種、こまめな掃除など、いくつかの対策を継続しておこなうことでリスクを下げることは可能です。
愛犬と散歩やキャンプなどアウトドアを楽しみつつ、犬も飼い主さんも安全に過ごせるよう、予防対策に取り組みましょう。
とくにマダニはあらゆるところに生息しているため、散歩のたびに寄生リスクがあるといえるでしょう。
しかし、駆除薬・予防薬、混合ワクチンの接種、こまめな掃除など、いくつかの対策を継続しておこなうことでリスクを下げることは可能です。
愛犬と散歩やキャンプなどアウトドアを楽しみつつ、犬も飼い主さんも安全に過ごせるよう、予防対策に取り組みましょう。