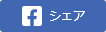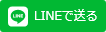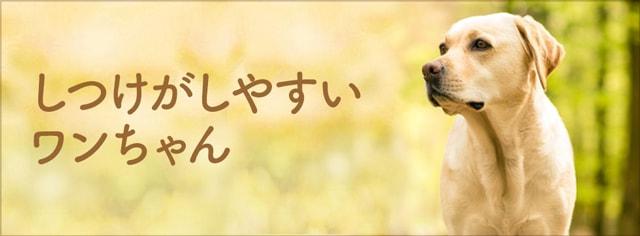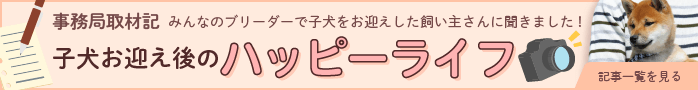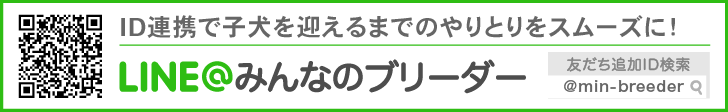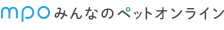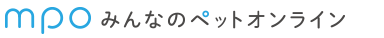犬の嘔吐とは?

犬がなにかを吐き出す動作には、「嘔吐」と「吐出」という2種類があります。一見同じように見えますが、原因も仕組みも違います。
嘔吐とは
嘔吐とは、脳内の嘔吐中枢が刺激されることによって起こります。「吐く」という信号が神経系統を通じて送られ、吐き気を催します。その後、横隔膜の収縮運動が起こり、胃や十二指腸の内容物が吐き出されるという仕組みです。
一度、胃の中に入り消化したものを吐くため、吐き出されたものは食べ物の一部が残っている場合もあれば、消化されて液体になっている場合もあります。
一度、胃の中に入り消化したものを吐くため、吐き出されたものは食べ物の一部が残っている場合もあれば、消化されて液体になっている場合もあります。
犬が嘔吐するときの前触れ
犬が嘔吐する前後には、下記のようなしぐさをすることが多いです。
- 頭を下げて吐きそうなしぐさをする
- 落ち着かない様子でソワソワと動き回る
- 草を食べる
- よだれを流す
- 飼い主さんから離れようとしない
- ぶるぶると具合が悪そうに震える
- 何度も飲み込むしぐさをする
- ペロペロと口周りを舐める
吐出(としゅつ)とは
吐出は、食道に炎症や腫瘍、異物、巨大食道症、血管輪異常などのトラブルがあり、胃に到達する前に食べ物や水、異物など飲み込んだものが吐き出されることをいいます。嘔吐と違い、吐き気がなく、食欲はあるため吐き出したものを食べてしまうこともあります。
しかし、再度、吐き出してしまう可能性もあるので、食べさせずに処理をしたほうがよいでしょう。
「おえ、おえ」と吐く前の予兆がある嘔吐に比べて、吐出は前触れなく吐き出すことも特徴です。
吐出はほとんどが病気によるもののため、吐出がみられた場合は早めに動物病院で診察を受けましょう。
しかし、再度、吐き出してしまう可能性もあるので、食べさせずに処理をしたほうがよいでしょう。
「おえ、おえ」と吐く前の予兆がある嘔吐に比べて、吐出は前触れなく吐き出すことも特徴です。
吐出はほとんどが病気によるもののため、吐出がみられた場合は早めに動物病院で診察を受けましょう。
犬の嘔吐の原因

犬が嘔吐するには、さまざまな原因が考えられます。
生理現象
食べたり飲んだりする勢いがあり過ぎたり、水をがぶ飲みしたりすると、急速に胃が拡張したことで嘔吐中枢を刺激し、嘔吐反射のきっかけになる可能性があります。
空腹
食事の間隔が長く空いたり、食事量や回数を減らしたりすると空腹の時間が長くなり、胃酸が出過ぎて胃液や泡を吐くことがあります。
中毒、感染症以外の病気
繰り返して嘔吐するときは、病気の可能性が高いです。
考えられる病気としては以下のようなものがあげられます。
<消化器系の病気>
<ホルモンやそのほかの臓器系の病気>
また薬を服用している場合、副作用によって消化器官が炎症を起こし、嘔吐している可能性もあるでしょう。
考えられる病気としては以下のようなものがあげられます。
<消化器系の病気>
- 胃捻転
- 腸捻転
- 腫瘍
- 胃拡張
- 潰瘍
- 胃腸炎
<ホルモンやそのほかの臓器系の病気>
- 尿毒症
- 糖尿病
- 糖尿病性ケトアシドーシス
- 副賢機能不全
- 子宮蓄膿症
- 前庭疾患(中耳炎や内耳炎)
- 脳炎
また薬を服用している場合、副作用によって消化器官が炎症を起こし、嘔吐している可能性もあるでしょう。
中毒
キシリトールやブドウ、チョコレートなど人間にとっては安全でも、犬にとっては危険な食べ物があります。ほかにも、除草剤や農薬がついた草、タバコなどを食べてしまった際は、中毒症状のひとつとして嘔吐している場合があります。
関連する記事
誤飲誤食
中毒を起こすものやおもちゃなどの異物を食べてしまうことにより、腸閉塞や消化管穿孔、粘膜などが刺激され、嘔吐することがあります。
感染症
寄生虫感染症
一部の寄生虫に感染すると胃炎に近い症状が出ます。感染した寄生虫の種類によっては、嘔吐物に白いひも状の虫が混じることもあるでしょう。
寄生虫の種類や寄生場所、寄生している数、宿主の状態などによって症状は変わりますが、嘔吐や下痢、血便、体重の減少、食欲の低下なども起こる場合があります。
寄生虫の種類や寄生場所、寄生している数、宿主の状態などによって症状は変わりますが、嘔吐や下痢、血便、体重の減少、食欲の低下なども起こる場合があります。
細菌、ウイルス感染症
犬パルボウイルスや犬コロナウイルスなどのウイルス感染症、細菌性腸炎やレプトスピラ症などの細菌感染症によって嘔吐をすることがあります。
ストレス
ストレス自体が嘔吐中枢を刺激すると考えられています。ほかにも自律神経の乱れから、消化液の分泌や消化管運動が乱れることも嘔吐のきっかけになる可能性があります。
ストレスの原因は、環境や食事内容の変化、飼い主とのコミュニケーション不足、運動不足、痛み、恐怖などさまざまです。
ストレスの原因は、環境や食事内容の変化、飼い主とのコミュニケーション不足、運動不足、痛み、恐怖などさまざまです。
食物アレルギー
食物アレルギーがある場合、食品に含まれたアレルゲンに反応して嘔吐することがあります。ごはんやおやつなどを変えた場合などは注意しましょう。
すぐに病院に行くべき犬の嘔吐

先ほど紹介したように犬の嘔吐には、さまざまな原因が考えられますが、なかにはすぐに病院を受診するなど迅速に対応したほうがいい症状もあります。病気や体調不良などの危険なサインを見逃さないようにしましょう。
繰り返し吐く
1日に何度も繰り返して吐いてしまう場合は、異物の誤飲や内臓・消化器系の病気が疑われます。また、嘔吐が繰り返される場合には低血糖や脱水症状を引き起こしたり、電解質の乱れの恐れもあります。とくに子犬はリスクが高いです。
下痢もしている
嘔吐の原因が消化器の異常や感染症の場合には下痢を伴うこともあります。嘔吐以外の症状がある場合には病気が疑われるため、受診することをおすすめいたします。
病気によっては症状が急激に進行する可能性もあるため、なるべく早く病院に相談しましょう。
病気によっては症状が急激に進行する可能性もあるため、なるべく早く病院に相談しましょう。
赤い血や黒っぽい血が混じっている
嘔吐物に血が混じっている場合は、口の中や食道、胃腸が傷ついている、炎症している、腫瘍などのできものができているなどの可能性が高いです。
吐物に血が混じる場合には、出血したばかりの血は鮮やかな赤に見えますが、時間がたつにつれて茶色~黒っぽくなります。また、出血量が少ないとピンク色に見えることもあります。
また、酸化し茶色くなった血液は、フードの色と判別が難しいこともあるので、診察時に嘔吐物を持っていくと、より正確な診断を受けることができます。
吐物に血が混じる場合には、出血したばかりの血は鮮やかな赤に見えますが、時間がたつにつれて茶色~黒っぽくなります。また、出血量が少ないとピンク色に見えることもあります。
また、酸化し茶色くなった血液は、フードの色と判別が難しいこともあるので、診察時に嘔吐物を持っていくと、より正確な診断を受けることができます。
異物が混じっている
嘔吐物にひもや綿、布切れなど異物が混じっている場合は、異物誤飲の可能性が高くなります。異物が腸に詰まると腸閉塞や腸穿孔などを引き起こす可能性もあるので、すぐに病院に行きましょう。
受診する際は、混ざっていた異物や飲み込んだと思われる物も一緒に持っていきましょう。もし吐き切れず異物の一部(ひもなど)が口から出ている場合は絶対に引っ張らないでください。内臓が傷つく恐れがあります。
受診する際は、混ざっていた異物や飲み込んだと思われる物も一緒に持っていきましょう。もし吐き切れず異物の一部(ひもなど)が口から出ている場合は絶対に引っ張らないでください。内臓が傷つく恐れがあります。
吐こうとしているのに吐けない
吐きたいのにうまく吐けない場合、ガスによって胃が膨れ上がる胃拡張や胃がねじれてしまう胃捻転の可能性があります。
食後数時間以内に発症することが多く、嘔吐だけでなく苦しがる、おなかが膨れる、そわそわと落ち着かないなどの症状が出ます。
命に関わる危険があり、緊急性が高いので、夜間の場合でも朝を待たずに病院に連れて行ってください。
食後数時間以内に発症することが多く、嘔吐だけでなく苦しがる、おなかが膨れる、そわそわと落ち着かないなどの症状が出ます。
命に関わる危険があり、緊急性が高いので、夜間の場合でも朝を待たずに病院に連れて行ってください。

移動中は安静に
原田 友紀先生
ワンちゃんが吐き出している際には嘔吐なのか、吐出なのかの判断が難しいことが多いです。しかしながら、いずれの場合であっても誤嚥が心配です。
病院への移動中の注意点としては、意識があるワンちゃんの場合には安静にし、ワンちゃんが楽な姿勢をとれるようにしてあげましょう。意識がないもしくは動けない状態の場合には、吐物が逆流しないように口元を少し下げるようにしてください。
また、移動中も吐くことがあるため、ペットシーツやタオルなどを十分に準備するのがおすすめです。ワンちゃんを抱っこする際には、頭を上げ過ぎず、おなかが圧迫されないように抱えるようにしましょう。
病院への移動中の注意点としては、意識があるワンちゃんの場合には安静にし、ワンちゃんが楽な姿勢をとれるようにしてあげましょう。意識がないもしくは動けない状態の場合には、吐物が逆流しないように口元を少し下げるようにしてください。
また、移動中も吐くことがあるため、ペットシーツやタオルなどを十分に準備するのがおすすめです。ワンちゃんを抱っこする際には、頭を上げ過ぎず、おなかが圧迫されないように抱えるようにしましょう。
様子を見てもいい嘔吐

嘔吐する原因のなかでも説明をしたように、緊急性がない嘔吐という場合があります。次のような嘔吐の場合は、自宅で様子を見ても大丈夫でしょう。
吐いても元気や食欲がある
嘔吐しても、その後、スッキリした様子で食欲が落ちていなければ問題ないことがほとんどです。
毛玉を吐いた
毛が抜けやすい時期などは被毛を飲みこみやすいです。飲み込んだ毛は消化できないため、便に混じって出てくるか、嘔吐によって出てきます。
吐いたあとも元気と食欲があり、嘔吐を繰り返さないのであれば生理現象の可能性が高いため、様子を見ても大丈夫でしょう。
ただし、まれに毛玉が原因で腸閉塞などを起こすこともあるため、毛玉を吐いてから嘔吐が止まらない、下痢が続いているなどの症状があれば、動物病院へ行きましょう。
吐いたあとも元気と食欲があり、嘔吐を繰り返さないのであれば生理現象の可能性が高いため、様子を見ても大丈夫でしょう。
ただし、まれに毛玉が原因で腸閉塞などを起こすこともあるため、毛玉を吐いてから嘔吐が止まらない、下痢が続いているなどの症状があれば、動物病院へ行きましょう。
空腹時に黄色い液体を少量吐いた
空腹の時間が長すぎると胃酸過多になり黄色い液体を吐くことがありますが、これは透明の胃液に胆汁が混ざったものといわれています。食事の間隔や頻度などを見直し、工夫をすることで落ち着いていきます。
1~2回しか嘔吐していない
1~2回嘔吐しても、苦しそうな様子やほかの症状がみられず、自然に落ち着いていくようであれば様子を見ていてよいでしょう。
車酔いで吐いた
乗り物に慣れていない犬や苦手な犬は、平衡感覚が乱れて少し車に乗っただけでも酔ってしまい、胃液がたくさん出て吐いてしまうことがあります。車を降りて治まるようであれば、車酔いである可能性が高いです。
症状が落ち着いているのであれば、様子をみても問題ないでしょう。
症状が落ち着いているのであれば、様子をみても問題ないでしょう。
草を食べて吐いた
犬は、興味から草を誤飲することもありますが、吐き気があるときなどに本能的に草を食べることがあります。草自体が胃腸に刺激を与え、嘔吐中枢を刺激する場合もあれば、付着していた成分(農薬や除草剤など)が原因で吐くこともあります。
一回草を吐くのみで、元気も食欲もある場合には、様子を見ても問題ないことが多いです。しかし何度も食べては吐くことを繰り返す場合はかかりつけ医に相談しましょう。
一回草を吐くのみで、元気も食欲もある場合には、様子を見ても問題ないことが多いです。しかし何度も食べては吐くことを繰り返す場合はかかりつけ医に相談しましょう。
勢いよく食べたり飲んだりした後に吐いた
もともと犬には勢いよく食事をする性質がありますが、食べたり飲んだりする勢いがあり過ぎると、急激に胃が大きくなり、嘔吐中枢が刺激され嘔吐してしまうことがあります。
犬が嘔吐したときの対処法

愛犬が嘔吐したとき、飼い主としてどのような対応をすればよいのでしょうか。対処法を紹介します。
絶食・絶飲をする
嘔吐した直後は、胃腸を休ませて次の嘔吐を防ぐためにいったんフード、水を片付けるようにしましょう。犬が欲しがっても嘔吐が治まるまで様子を見て、最初は水を少しだけあげることからはじめてください。
もし、水分を取っても嘔吐しなければ、ふやかしたドライフードやウェットフードを少しずつあげてみましょう。
その後も念のため食事を3~4回に分けて与え、徐々にいつもの食事回数に戻していきます。脱水症状にならないように注意しましょう。
しかし、子犬の場合は低血糖や脱水の恐れがあるため、自己判断で絶飲、絶食をおこなわず、病院に行きましょう。
もし、水分を取っても嘔吐しなければ、ふやかしたドライフードやウェットフードを少しずつあげてみましょう。
その後も念のため食事を3~4回に分けて与え、徐々にいつもの食事回数に戻していきます。脱水症状にならないように注意しましょう。
しかし、子犬の場合は低血糖や脱水の恐れがあるため、自己判断で絶飲、絶食をおこなわず、病院に行きましょう。
病院へ連れて行く
下痢、食欲不振、苦しそうなしぐさなど、吐く以外の症状の有無や愛犬の状態を見て病院へ行くかどうかを判断します。判断に迷うときは、動物病院へ連れて行ったほうが安心です。
連れて行く際は、吐いたときの状況や原因をなるべく正確に伝えられるようにしましょう。可能であれば嘔吐物を持参したほうがいいですが、難しいようであれば嘔吐した状況や嘔吐物を動画や写真で撮影していくのがおすすめです。
連れて行く際は、吐いたときの状況や原因をなるべく正確に伝えられるようにしましょう。可能であれば嘔吐物を持参したほうがいいですが、難しいようであれば嘔吐した状況や嘔吐物を動画や写真で撮影していくのがおすすめです。
便の状態を確認する
嘔吐だけでなく下痢や軟便も引き起こしていないか、注意深く観察しましょう。便に異常があれば、嘔吐物だけでなく便も持参して受診をしてください。また、下痢を併発している場合、脱水症状の心配があります。
少しずつ水分を与えることができればいいですが、もし、水分を取ることができないようであれば、病院で点滴などの処置を受けることになるかもしれません。
少しずつ水分を与えることができればいいですが、もし、水分を取ることができないようであれば、病院で点滴などの処置を受けることになるかもしれません。
隔離する
嘔吐の原因が寄生虫や細菌、ウイルスなどの感染症の場合も考えられます。2頭以上を一緒に飼っている場合、未感染の犬へと感染が拡大しないように、疑いが晴れるまで隔離をするようにしましょう。
また、感染した犬の便や嘔吐したものを舐めたり、触れたりしないように室内や犬用の食器、感染した犬や嘔吐物に接した飼い主さんの衣類などを消毒することも大切です。
また、感染した犬の便や嘔吐したものを舐めたり、触れたりしないように室内や犬用の食器、感染した犬や嘔吐物に接した飼い主さんの衣類などを消毒することも大切です。
掃除をする
犬の嘔吐物の掃除方法は、吐いた場所などによって多少異なります。
基本的には嘔吐した固形物や液体などを取り除き、その後、洗濯できるものは洗濯、洗濯ができないものや床は嘔吐物が残らないように、濡らした雑巾などでよく拭くようにしてください。
嘔吐してから時間がたってしまい、嘔吐物が乾いてしまった場合には、取れる範囲で嘔吐物を取り除き、こびりついている部分をふやかしてから掃除するとよいでしょう。
また、掃除後も臭いが気になる場合は、ペット用の消臭・除菌スプレーや重曹水(重曹小さじ1:水500ml)をスプレーして、拭き取ることを繰り返していくと徐々に臭いが薄れていきます。
基本的には嘔吐した固形物や液体などを取り除き、その後、洗濯できるものは洗濯、洗濯ができないものや床は嘔吐物が残らないように、濡らした雑巾などでよく拭くようにしてください。
嘔吐してから時間がたってしまい、嘔吐物が乾いてしまった場合には、取れる範囲で嘔吐物を取り除き、こびりついている部分をふやかしてから掃除するとよいでしょう。
また、掃除後も臭いが気になる場合は、ペット用の消臭・除菌スプレーや重曹水(重曹小さじ1:水500ml)をスプレーして、拭き取ることを繰り返していくと徐々に臭いが薄れていきます。

嘔吐や吐出時は飼い主が柔軟な対応を
原田 友紀先生
嘔吐や吐出では誤嚥も心配です。吐いてほしくない場所で吐き出そうとしていても、嘔吐中のワンちゃんを抱っこしたり、動かしたりしないようにしましょう。
間に合いそうな場合は口元にペットシーツやタオル、ビニールなどを置き、吐物をキャッチしてもいいかもしれません。また、嘔吐は反射で起きてしまうため、ワンちゃんを叱らないであげてください。
間に合いそうな場合は口元にペットシーツやタオル、ビニールなどを置き、吐物をキャッチしてもいいかもしれません。また、嘔吐は反射で起きてしまうため、ワンちゃんを叱らないであげてください。
犬の嘔吐予防法

いくら心配がない嘔吐もあるとはいえ、できれば予防をしたいですよね。下記のような方法を試してみましょう。
ブラッシングやシャンプー
毛玉を吐くような場合、ブラッシングやシャンプーなどで抜け落ちる前の毛を取り去るのが効果的です。毛が抜け変わる時期は、こまめに掃除機をかけるなどして床の毛やほこりも取り除くようにしましょう。
食事を与える回数を増やす
空腹時に吐いてしまう、一気に食べて吐いてしまうような子には、1回の食事量を減らして、回数を増やす、わんこそば方式で与えるなどの方法を試してみましょう。早食い防止の食器やノーズワーク、知育トイなどを取り入れるのも効果的です。
ストレス対策をする
愛犬の気持ちになって生活環境を見直し、負担になっていることはないか考えてみてください。ひとりで留守番する時間を短くする、コミュニケーションや散歩の時間を取るなど、いろいろと工夫してみましょう。
誤飲・誤食対策を徹底する
家の中を見直して誤食しそうなものは片づける、人の食事の食べ残しをテーブルなどに置きっぱなしにしないなどの習慣をつけるようにしましょう。ゴミ箱を蓋つきにするのもおすすめです。
また、犬をおもちゃで遊ばせる際には、目を離さないようにし、遊び終わったおもちゃは必ず犬が届かない場所にしまいましょう。
散歩中の拾い食いにも注意が必要です。
また、犬をおもちゃで遊ばせる際には、目を離さないようにし、遊び終わったおもちゃは必ず犬が届かない場所にしまいましょう。
散歩中の拾い食いにも注意が必要です。

完全な予防は無理でも、対策は可能
原田 友紀先生
嘔吐はさまざまな原因で起こるため、完全に予防することは難しいです。しかしながら、異物誤飲や感染症などは予防できる可能性が高いです。まずはおうちの中のほかに、お散歩やドッグランなどのお出かけ先で誤飲をしやすい場所がないか洗い出してみましょう。
お掃除をする、誤飲しそうな散歩コースを避ける、口に入れたものを出すトレーニングをするなどによって誤飲による嘔吐予防が期待できます。
また、レプトスピラ症や犬コロナウイルス感染症などは混合ワクチン接種で予防ができます。混合ワクチンの接種についてはかかりつけの先生に相談してみましょう。
お掃除をする、誤飲しそうな散歩コースを避ける、口に入れたものを出すトレーニングをするなどによって誤飲による嘔吐予防が期待できます。
また、レプトスピラ症や犬コロナウイルス感染症などは混合ワクチン接種で予防ができます。混合ワクチンの接種についてはかかりつけの先生に相談してみましょう。
獣医師に聞いた! 犬の嘔吐に関するQ&A
1日に1~2回吐く状態が3日間ほど続いている。病院に行くべき?
心配な状況ですね。通常、1~2回の嘔吐があって、翌日以降は症状が続かない場合には問題ないことが多いです。ですが、翌日も同様の症状があれば、なんらかの異常が疑われるため、受診するのが望ましいと思います。
多頭飼いで誰が嘔吐したのかわからない。全員を病院に連れて行ってもいい?
多頭飼いでは吐いている瞬間を目撃していない場合には、どの子の吐物か判断が難しいですよね。ですが、吐物が連日目撃されている、吐物が何カ所にもあるなど嘔吐が続いている場合には、症状のある子が未特定の場合でも受診するのが理想的です。
全頭の受診が難しい場合には、数匹ずつに部屋を分けて様子を見る、見守りカメラを設置する、往診を依頼するなどもご検討ください。
全頭の受診が難しい場合には、数匹ずつに部屋を分けて様子を見る、見守りカメラを設置する、往診を依頼するなどもご検討ください。
嘔吐物を食べたがる。食べても大丈夫?
異物や中毒性のある物質などが混じっていない限りは再度食べても問題ないことがほとんどです。
ですが、再び吐く恐れもあるため、食べてしまった場合には30分~1時間ほどは吐かないかよく様子を見てあげましょう。
ですが、再び吐く恐れもあるため、食べてしまった場合には30分~1時間ほどは吐かないかよく様子を見てあげましょう。
運動後によく吐く。病気? 予防法や対処法はある?
食後に運動をして吐いてしまう場合は、生理現象や胃拡張胃捻転などが考えられます。食後2,3時間は運動を控えましょう。
食後時間が経過しているのに吐いてしまう場合には三半規管の異常なども考えられます。一度ご受診することをおすすめいたします。
食後時間が経過しているのに吐いてしまう場合には三半規管の異常なども考えられます。一度ご受診することをおすすめいたします。
獣医師からのメッセージ
ワンちゃんがはじめて吐いたときはとっても驚くと思います。また、吐いている最中のワンちゃんを見守ることも辛いと思いますが、なるべくワンちゃんを動かさず、本人の楽な姿勢で、好きな場所で吐き出し終えるのを待ちましょう。
今後、もし嘔吐を目撃したときはなるべく記録を残すのがおすすめです。日付や時間、吐いた中身、写真などを残しておくと今後症状が続いたときの参考になることが多いです。ぜひかかりつけ医にも記録した内容を共有してみてください。
嘔吐は生理現象から命に関わる病気まで、その原因が多岐にわたるからこそ不安も多いと思います。生理現象の嘔吐か判断が難しい場合は、かかりつけ医に相談しましょう。
今後、もし嘔吐を目撃したときはなるべく記録を残すのがおすすめです。日付や時間、吐いた中身、写真などを残しておくと今後症状が続いたときの参考になることが多いです。ぜひかかりつけ医にも記録した内容を共有してみてください。
嘔吐は生理現象から命に関わる病気まで、その原因が多岐にわたるからこそ不安も多いと思います。生理現象の嘔吐か判断が難しい場合は、かかりつけ医に相談しましょう。
まとめ

今回紹介した以外にも子犬は消化器官が整っていない、老犬は消化力や筋力が落ちてきている、などの理由で吐いてしまうこともあります。犬の様子をよく観察し、いち早く異常に気が付けるようにすることが大切です。獣医師の力も借りながら悪化させないようにしていきましょう。