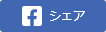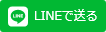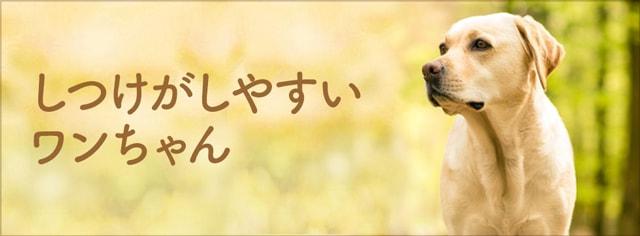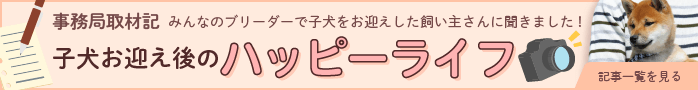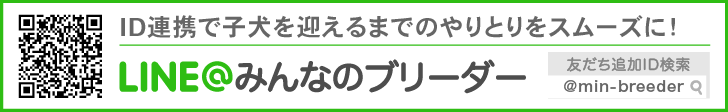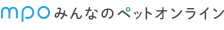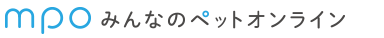🔍この記事でわかること
・ブリーダーの仕事と必要資格
・ブリーダーから子犬を迎える流れ
・優良ブリーダーの選び方と注意点
・ブリーダーの仕事と必要資格
・ブリーダーから子犬を迎える流れ
・優良ブリーダーの選び方と注意点
犬のブリーダーとは

犬のブリーダーとは、犬を繁殖・飼育する専門家です。犬を交配させるだけでなく、親犬や子犬を飼育し、お客様に販売するのも仕事の一つです。
家族で運営していたり、スタッフを雇っていたりと、ブリーダーによって規模は異なります。
家族で運営していたり、スタッフを雇っていたりと、ブリーダーによって規模は異なります。
ブリーダーの仕事内容
ブリーダーの仕事は、犬の飼育・繁殖から販売、アフターケアに至るまで多岐にわたります。
健康で社会性のある子犬を育てるため、毎日の食事管理やお手入れ、トイレやケージの掃除、散歩やしつけなどのきめ細やかなケアが欠かせません。
繁殖においては、血統や遺伝性疾患に関する知識をもとに、計画的な交配をおこないます。出産時の立ち合いや、生まれた子犬と母犬の体調管理といった産後のケアも大切な仕事です。
近年では、子犬の販売方法も多様化しており、ペットオークションを介した販売に加えて、WebサイトやSNSを通じてお客様と直接やりとりするケースも増えています。
直接販売の場合は、子犬の迎え入れに関する説明をおこなうほか、飼育やしつけについてアドバイスすることもあり、その後の相談に応じるなど、丁寧な対応が求められます。
健康で社会性のある子犬を育てるため、毎日の食事管理やお手入れ、トイレやケージの掃除、散歩やしつけなどのきめ細やかなケアが欠かせません。
繁殖においては、血統や遺伝性疾患に関する知識をもとに、計画的な交配をおこないます。出産時の立ち合いや、生まれた子犬と母犬の体調管理といった産後のケアも大切な仕事です。
近年では、子犬の販売方法も多様化しており、ペットオークションを介した販売に加えて、WebサイトやSNSを通じてお客様と直接やりとりするケースも増えています。
直接販売の場合は、子犬の迎え入れに関する説明をおこなうほか、飼育やしつけについてアドバイスすることもあり、その後の相談に応じるなど、丁寧な対応が求められます。
ブリーダーになるには?|必要な資格・経験
現在、日本では犬のブリーダーになるために特別な資格は必要ありません。
ブリーダーとして開業する場合、「第一種動物取扱業」の取得が必要です。この資格を得るためには、十分な飼育設備を整えることが求められるほか、動物専門学校の卒業資格や半年以上の関連業界での勤務実績も必要とされます。
ブリーダーになるには、動物・ペット専門の専門学校に通うか、信頼できるブリーダーのもとで働きながら学ぶか、いずれかの方法で、動物の健康管理、お世話やしつけの方法などを体系的に学ぶ必要があるのです。
ブリーダーとして開業する場合、「第一種動物取扱業」の取得が必要です。この資格を得るためには、十分な飼育設備を整えることが求められるほか、動物専門学校の卒業資格や半年以上の関連業界での勤務実績も必要とされます。
ブリーダーになるには、動物・ペット専門の専門学校に通うか、信頼できるブリーダーのもとで働きながら学ぶか、いずれかの方法で、動物の健康管理、お世話やしつけの方法などを体系的に学ぶ必要があるのです。
ブリーダーは儲かる?
ブリーダーの収入は、ブリーダーとしてのスキル、そして事業規模によって大きく変わります。
たとえば、広い飼育環境を整えて多数の犬を管理している場合、安定した収益につながる可能性もあります。
ただし、ブリーダー業には日々の食事管理や医療ケア、水道光熱費やワクチン費用、人件費など、さまざまな経費がかかります。そこから手元に残る金額が、いわゆる「年収」となります。
また、飼育の知識や倫理的な配慮、誠実な接客対応も欠かせません。平日も休日も関係なく、動物たちの命と向き合い続ける必要があるため、「好き」だけでは続けられない側面もあります。
収益を上げるには、しっかりとした経営視点と、犬の幸せを第一に考える姿勢の両立が求められます。
関連する記事
たとえば、広い飼育環境を整えて多数の犬を管理している場合、安定した収益につながる可能性もあります。
ただし、ブリーダー業には日々の食事管理や医療ケア、水道光熱費やワクチン費用、人件費など、さまざまな経費がかかります。そこから手元に残る金額が、いわゆる「年収」となります。
また、飼育の知識や倫理的な配慮、誠実な接客対応も欠かせません。平日も休日も関係なく、動物たちの命と向き合い続ける必要があるため、「好き」だけでは続けられない側面もあります。
収益を上げるには、しっかりとした経営視点と、犬の幸せを第一に考える姿勢の両立が求められます。
ブリーダーから迎えるメリット

適正価格で迎えられる
オークションやペットショップなどの中間業者が関わる場合、人件費や仲介手数料が加算されます。一方、ブリーダーから直接お迎えする場合は中間業者を介さないため、子犬本来の価格で適正に販売されます。
ただし、適正価格=「安い」というわけではありません。人気の犬種や血統、犬種標準にどれだけ近いかなども価格に影響することを覚えておきましょう。
ただし、適正価格=「安い」というわけではありません。人気の犬種や血統、犬種標準にどれだけ近いかなども価格に影響することを覚えておきましょう。
子犬が社会性を身につけた状態で迎えられる
子犬が社会性を学ぶ重要な時期は、生後約3カ月までといわれています。この時期に親犬や兄弟犬と十分に触れ合い、スキンシップや遊びを通して社会性が培われます。
犬の噛み癖に悩む飼い主は少なくありませんが、犬同士で遊ぶことで、噛む力加減や他者との適切な関わり方を学ぶため、噛み癖を含む問題行動が少ない子に育つことが期待されます。
また、ブリーダーとの交流を通じて、人間との接し方も学んでいきます。
犬の噛み癖に悩む飼い主は少なくありませんが、犬同士で遊ぶことで、噛む力加減や他者との適切な関わり方を学ぶため、噛み癖を含む問題行動が少ない子に育つことが期待されます。
また、ブリーダーとの交流を通じて、人間との接し方も学んでいきます。
プロであるブリーダーから直接アドバイスがもらえる
迎えたい犬種のプロであるブリーダーから飼育に関するアドバイスを受けられるのは、とても貴重な機会です。
性格や体の特徴、生活リズム、しつけの方法など、気になることがあれば積極的に質問してみましょう。丁寧に教えてくれるはずです。
お迎え直後は、子犬の体調や環境の整え方など、飼い主にとって分からないことも多いかもしれません。 引き渡し後も、ブリーダーにとって子犬は大切な存在。飼い主が気軽に相談できる手段を提供してくれることが多いです。
関連する記事
性格や体の特徴、生活リズム、しつけの方法など、気になることがあれば積極的に質問してみましょう。丁寧に教えてくれるはずです。
お迎え直後は、子犬の体調や環境の整え方など、飼い主にとって分からないことも多いかもしれません。 引き渡し後も、ブリーダーにとって子犬は大切な存在。飼い主が気軽に相談できる手段を提供してくれることが多いです。
犬のブリーダーの探し方から、子犬を迎えるまで

ブリーダーサイトで子犬を探す
子犬登録数が豊富なブリーダー直販サイトなら、たくさんの選択肢のなかから気になる子犬を探すことができます。
子犬登録数、実績数、ユーザーの口コミ数が共に高い『みんなのブリーダー』では、さまざまな犬種が常時掲載されています。サイトでは効率的に子犬を探せるだけでなく、顔立ちや体格、性格など、ブリーダーが提供する詳細な情報を確認できます。
『みんなのブリーダー』で掲載中の子犬を見てみる
子犬登録数、実績数、ユーザーの口コミ数が共に高い『みんなのブリーダー』では、さまざまな犬種が常時掲載されています。サイトでは効率的に子犬を探せるだけでなく、顔立ちや体格、性格など、ブリーダーが提供する詳細な情報を確認できます。
『みんなのブリーダー』で掲載中の子犬を見てみる
ブリーダーに問い合わせる
サイトなどでお気に入りの子を見つけ、子犬についてブリーダーに確認したいことがあれば、気軽に問い合わせてみましょう。
気になったことや疑問点をブリーダーに聞いて、納得したうえで子犬を迎えることをおすすめします。
気になったことや疑問点をブリーダーに聞いて、納得したうえで子犬を迎えることをおすすめします。
犬舎を見学する
犬舎とは、ブリーダーが複数の犬を飼育している場所のことです。
動物愛護管理法によって、ブリーダーは販売する動物を直接購入者に見せ、飼育方法や生年月日などの説明を対面でおこなうことが義務付けられています。そのため、ブリーダーから子犬を迎える際は、原則として犬舎を見学する必要があります。
犬舎見学の際は、事前予約が必要です。予約方法は、電話やメール、またはサイトの予約フォームなど、ブリーダーによって異なります。
また、感染症対策として、ペットショップやほかの犬舎に立ち寄ってからの訪問を控えるよう求める場合も少なくありません。見学に行く前には、ブリーダーが提示している注意事項をしっかり確認しましょう。
関連する記事
動物愛護管理法によって、ブリーダーは販売する動物を直接購入者に見せ、飼育方法や生年月日などの説明を対面でおこなうことが義務付けられています。そのため、ブリーダーから子犬を迎える際は、原則として犬舎を見学する必要があります。
犬舎見学の際は、事前予約が必要です。予約方法は、電話やメール、またはサイトの予約フォームなど、ブリーダーによって異なります。
また、感染症対策として、ペットショップやほかの犬舎に立ち寄ってからの訪問を控えるよう求める場合も少なくありません。見学に行く前には、ブリーダーが提示している注意事項をしっかり確認しましょう。
契約(予約)からお迎えの日まで
犬舎を見に行き、犬を迎えることを決めた場合、見学時点で生後56日を過ぎていれば、当日に子犬を連れて帰ることが可能です(8週齢規制)。
ただし、お迎えまでの流れは、ブリーダーによって対応が異なる場合もありますので、見学当日にお迎えを希望する場合は、事前にブリーダーに相談しましょう。
※柴犬や秋田犬などの天然記念物に指定されている日本犬については、ブリーダーからの直接購入に限り規制の基準が異なる場合があります。
ただし、自治体やブリーダーによって運用が異なることもあるため、事前に犬舎や自治体へ確認することが大切です。
ただし、お迎えまでの流れは、ブリーダーによって対応が異なる場合もありますので、見学当日にお迎えを希望する場合は、事前にブリーダーに相談しましょう。
※柴犬や秋田犬などの天然記念物に指定されている日本犬については、ブリーダーからの直接購入に限り規制の基準が異なる場合があります。
ただし、自治体やブリーダーによって運用が異なることもあるため、事前に犬舎や自治体へ確認することが大切です。
ブリーダーとのやり取りのマナーや注意点
犬舎見学に行く際は、次のような点に気を付けましょう。
関連する記事
- 見学は事前予約し、約束を守る(ドタキャンはNG)
- 1日で複数のブリーダーを回らない(病気を持ち込んだり、広めたりする原因になる)
- 犬舎では許可なしに親犬や子犬を触らない
- 無理やり抱き上げたり、犬が嫌がったりするようなことはしない
- 「かわいい子犬を見に行きたいから」という理由で見に行かない
優良ブリーダーの見分け方

ブリーダーは犬の命を預かる責任の重い仕事です。優良ブリーダーは、犬のことを真剣に考え、豊富な知識と経験に基づき犬種の保存に心血を注いでいます。
信頼できるブリーダーを探す際は、次のようなポイントを確認するとよいでしょう。
関連する記事
信頼できるブリーダーを探す際は、次のようなポイントを確認するとよいでしょう。
- 動物愛護管理法についてきちんと理解している(繁殖回数の制限、ケージの広さ、スタッフの人数など)
- 適切なブリーディングや飼育をしている
- 血統情報を教えてくれる
- お迎え方法や飼育方法について十分な説明やアドバイスをくれる
- 質問に対して丁寧に回答してくれる
まとめ

ブリーダーは犬の繁殖と飼育のプロであり、愛犬家でもあります。ブリーダーから直接お迎えする場合、健康で相性のよい子犬を迎えられるだけでなく、お迎え前の疑問や不安にも親身に対応してくれるでしょう。
お迎え後も、食事やしつけで困った際に丁寧にアフターフォローをしてくれるブリーダーが多くいます。長く一緒に暮らす大切な家族として迎えるからこそ、信頼できるブリーダーと出会うことが大切です。
お迎え後も、食事やしつけで困った際に丁寧にアフターフォローをしてくれるブリーダーが多くいます。長く一緒に暮らす大切な家族として迎えるからこそ、信頼できるブリーダーと出会うことが大切です。