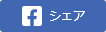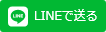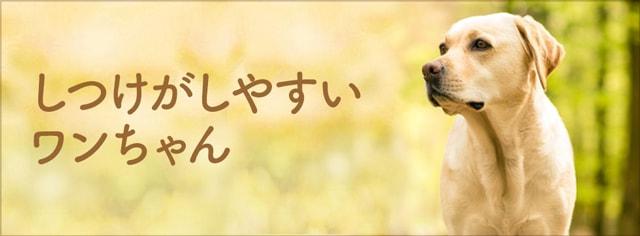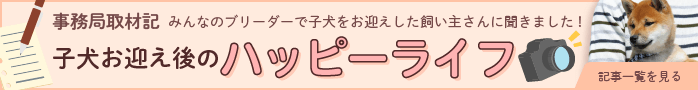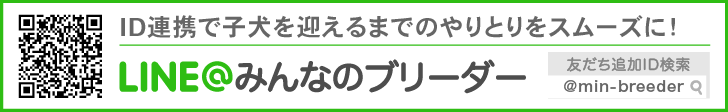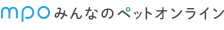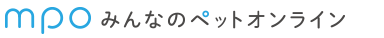犬のフィラリア症ってなに?

フィラリアとは、「犬糸状虫(いぬしじょうちゅう)」という寄生虫のこと。成虫は、約15~30cmの白いそうめんのような形をしています。
フィラリア症ってどんな病気?
犬のフィラリア症は、フィラリアに感染した蚊に刺されることが原因の病気です。すでにフィラリア症に感染している蚊が犬を吸血することで、体内にフィラリアの幼虫(ミクロフィラリア)が入り込み感染します。犬同士の接触で感染することはなく、蚊を媒介して感染が広がります。
犬の体内に入り込んだ幼虫は、脱皮を繰り返しながら成長。感染してから約4カ月後に血管を通して血流に乗り、心臓の右心室や肺動脈に移動し成虫になります。犬の体内に入り込んでから約6カ月後、成虫になったフィラリアは、新たな幼虫を産み、血液中に幼虫が現れはじめます。
そして、感染に気が付かず放置しておくと心臓のほか肺や肝臓、腎臓、血管などに影響を及ぼし最悪、死に至る可能性もあるほど怖い病気です。
また、幼虫(ミクロフィラリア)が血液中にいる状態の犬が蚊に刺されると、蚊にフィラリアが寄生し、その蚊がほかの犬を刺すことでフィラリア症は広がっていきます。
犬の体内に入り込んだ幼虫は、脱皮を繰り返しながら成長。感染してから約4カ月後に血管を通して血流に乗り、心臓の右心室や肺動脈に移動し成虫になります。犬の体内に入り込んでから約6カ月後、成虫になったフィラリアは、新たな幼虫を産み、血液中に幼虫が現れはじめます。
そして、感染に気が付かず放置しておくと心臓のほか肺や肝臓、腎臓、血管などに影響を及ぼし最悪、死に至る可能性もあるほど怖い病気です。
また、幼虫(ミクロフィラリア)が血液中にいる状態の犬が蚊に刺されると、蚊にフィラリアが寄生し、その蚊がほかの犬を刺すことでフィラリア症は広がっていきます。
どんな犬がかかりやすい? 犬以外にも感染する?
フィラリア症にかかりやすい犬種、年齢はありません。予防すればほぼ感染することはありませんが、予防しないとフィラリアに感染する確率は格段に上がります。
川沿いや水辺といった蚊の多い地域や野外の飼育では、蚊に刺されるリスクが高く感染率も上がります。
犬以外では猫やフェレット、タヌキなども感染することがあり、ごくまれに人間が感染することもあります。
川沿いや水辺といった蚊の多い地域や野外の飼育では、蚊に刺されるリスクが高く感染率も上がります。
犬以外では猫やフェレット、タヌキなども感染することがあり、ごくまれに人間が感染することもあります。

屋内飼育でも油断は禁物
原田 友紀先生
最近では高層マンションなどの屋内にも蚊がいるので、屋内で飼育していてもフィラリアに感染する可能性があります。屋外で飼育しているわんちゃんと比べると感染する可能性は低いですが、基本的に薬での予防が必要です。
犬がフィラリア症にかかったら、どんな症状が出る?

フィラリアが寄生すると心臓や肺、血管など犬の体に重篤なダメージを与えます。そして、この病気が厄介なのは初期ではなかなか気が付きにくいという点です。
症状が現われはじめる時期については断定できませんが、数年で発症することが多いようです。そして、症状に気付いたときにはすでに重症化している可能性もあります。
症状が現われはじめる時期については断定できませんが、数年で発症することが多いようです。そして、症状に気付いたときにはすでに重症化している可能性もあります。
フィラリアの初期症状
初期段階では、無症状である場合がほとんどです。
フィラリアの中期症状
中期になると、幼虫が心臓内で成長すると、心臓の血流を邪魔してしまったり、心臓の弁を傷つけてしまうため、咳、歩きたがらない、元気がない、息が荒くなるといった心不全に近い症状が現れはじめます。
フィラリアの末期症状
末期になると腹水、血尿、四肢のむくみ、吐血、呼吸困難といった症状が現われ、適切な処置をおこなわないと死に至ることもあります。
まれに、「急性フィラリア症」を発症することで、急激に悪化するケースも。発症すると、苦しそうに呼吸をしたり、食欲がなくなってしまったり、血のようなおしっこが出たりといったショック状態に陥ります。その場合には、助からないことがほとんどです。
まれに、「急性フィラリア症」を発症することで、急激に悪化するケースも。発症すると、苦しそうに呼吸をしたり、食欲がなくなってしまったり、血のようなおしっこが出たりといったショック状態に陥ります。その場合には、助からないことがほとんどです。
犬にフィラリア症の疑いがある場合の検査方法は?

犬がフィラリア症に感染しているかどうかは、動物病院での血液検査でわかります。
顕微鏡検査
血液中にフィラリアの幼虫が存在するかどうか、顕微鏡で血液を見て調べる検査です。
幼虫は日中よりも夜間に量が増える性質があるため、夕方以降に検査をする方が検出率が上がります。
幼虫は日中よりも夜間に量が増える性質があるため、夕方以降に検査をする方が検出率が上がります。
抗原検査
フィラリアの成虫から分泌される物質が血液中に含まれているかを専用のキットを用いて調べる検査で、数滴の血液で検査ができます。感度が良く、ほとんどの動物病院で用いられている検査方法です。
どちらの検査も血液の採取から数分で結果が出ます。
血液検査でフィラリア感染が確認された場合、あるいはすでに症状が現われている場合は、病気の進行度合いを詳しく調べるためX線検査、超音波検査、血液検査、尿検査などが追加でおこなわれます。
どちらの検査も血液の採取から数分で結果が出ます。
血液検査でフィラリア感染が確認された場合、あるいはすでに症状が現われている場合は、病気の進行度合いを詳しく調べるためX線検査、超音波検査、血液検査、尿検査などが追加でおこなわれます。
予防前に検査をしましょう
次章ではフィラリア予防について紹介しますが、予防をはじめる前に必ずフィラリア感染の有無を調べるための血液検査をおこないます。予防薬には幼虫を駆除する成分が含まれ、幼虫が数匹単位であれば、ほぼ問題ありません。
しかし、すでに成虫が心臓に寄生し、血液中に幼虫が存在していると、一度に大量の幼虫が死滅してしまい、それが毛細血管に詰まってショック死してしまうこともあります。
そのため、フィラリア症の検査は予防薬をはじめる前に必ず受けることをおすすめします。
しかし、すでに成虫が心臓に寄生し、血液中に幼虫が存在していると、一度に大量の幼虫が死滅してしまい、それが毛細血管に詰まってショック死してしまうこともあります。
そのため、フィラリア症の検査は予防薬をはじめる前に必ず受けることをおすすめします。
犬のフィラリア症の予防法は?

フィラリア症の予防期間は、蚊の活動がはじまる1カ月後から蚊がいなくなる1カ月後までです。
蚊の活動期間により予防するため、地域によってその期間に多少の違いがみられます。
フィラリア症は薬で予防しますが、薬のタイプもさまざまです。それぞれ特徴が異なるので、犬の性格や体質などに合わせて選んでくださいね。
蚊の活動期間により予防するため、地域によってその期間に多少の違いがみられます。
- 関東地方:5~12月ごろ
- 北海道:7~11月ごろ
- 東北地方:6~11月ごろ
- 北陸・東海地方:5~12月ごろ
- 近畿地方:5~12月ごろ
- 中国・四国地方:5~12月ごろ
- 九州・沖縄地方:5~12月ごろ
フィラリア症は薬で予防しますが、薬のタイプもさまざまです。それぞれ特徴が異なるので、犬の性格や体質などに合わせて選んでくださいね。
錠剤
フィラリアの感染予防と幼虫に対する駆除効果(フィラリア単独予防)があり、月1回の投薬で費用はほかの予防薬よりも比較的安価。
食物アレルギーのある犬や皮膚が弱い犬も使用できることもメリットです。
また、フィラリアだけでなく、おなかの寄生虫に効果がある成分が含まれているものもあります。
フードやおやつに包んで与えるか、直接喉の奥に押し込んで飲ませましょう。味覚が繊細な犬は吐き出してしまう場合もあるので、投薬後はしっかり観察することが必要です。
食物アレルギーのある犬や皮膚が弱い犬も使用できることもメリットです。
また、フィラリアだけでなく、おなかの寄生虫に効果がある成分が含まれているものもあります。
フードやおやつに包んで与えるか、直接喉の奥に押し込んで飲ませましょう。味覚が繊細な犬は吐き出してしまう場合もあるので、投薬後はしっかり観察することが必要です。
チュアブル
嗜好性の高いおやつタイプなので、錠剤に比べて飲ませやすいという特徴があります。ただし、食物アレルギーのある犬は必ず獣医師に相談しましょう。
フィラリア単独予防に有効なものはもちろん、ノミ・マダニや、おなかの寄生虫なども一緒に予防できるオールインワンタイプも人気です。
フィラリア単独予防に有効なものはもちろん、ノミ・マダニや、おなかの寄生虫なども一緒に予防できるオールインワンタイプも人気です。
スポット薬
駆虫成分の入った薬液を首の後ろに塗布し、皮膚から成分を吸収させます。
フィラリアだけでなく、ノミ・マダニ・おなかの寄生虫などの予防が一度にできるものが一般的です。食物アレルギーのある犬にも使用可能で、吐き出す心配がないので確実に投薬ができます。
スポット薬の投薬後は2~3日、シャンプーや水浴びを避けましょう。
フィラリアだけでなく、ノミ・マダニ・おなかの寄生虫などの予防が一度にできるものが一般的です。食物アレルギーのある犬にも使用可能で、吐き出す心配がないので確実に投薬ができます。
スポット薬の投薬後は2~3日、シャンプーや水浴びを避けましょう。
注射薬
皮下注射(フィラリア単独予防)は通常ほかの予防薬より費用がかかりますが、年に1回の注射で通年予防ができるという大きなメリットがあります。
また、投薬忘れの心配もなくなります。
また、投薬忘れの心配もなくなります。
犬フィラリア症の治療法

消化器官に寄生する虫と異なり、フィラリアは肺につながる血管と、心臓に寄生します。
もし体内にフィラリアが認められる場合には、すでに血管や心臓に負荷がかかっていると考えられます。
また、寄生しているフィラリアが大量だった場合、一気に駆虫すると心臓や血管などの体内組織に重大な損傷をもたらす可能性も……。したがって、フィラリア症の治療には慎重な判断が求められます。
もし体内にフィラリアが認められる場合には、すでに血管や心臓に負荷がかかっていると考えられます。
また、寄生しているフィラリアが大量だった場合、一気に駆虫すると心臓や血管などの体内組織に重大な損傷をもたらす可能性も……。したがって、フィラリア症の治療には慎重な判断が求められます。
成虫用駆虫薬の投与
成虫は通常の予防薬では駆虫することができないため、成虫用の薬が必要です。
ただし、重度のフィラリア症の場合は、駆虫薬の投与で犬が死亡する危険性も高いので、検査結果によっては実施できないこともあります。
その場合には、一気に駆虫せずに、少しずつ弱らせていくような投薬方法をとることもあり、治療期間は数カ月~1年半以上かかる場合もあります。
ただし、重度のフィラリア症の場合は、駆虫薬の投与で犬が死亡する危険性も高いので、検査結果によっては実施できないこともあります。
その場合には、一気に駆虫せずに、少しずつ弱らせていくような投薬方法をとることもあり、治療期間は数カ月~1年半以上かかる場合もあります。
予防薬の長期投与
目に見える症状がなく、成虫の数も少ない場合に用いられる治療法。フィラリアの自然な減少を待つため殺虫率は低く、年単位という長期間の投与が必要です。
フィラリア死滅による副作用を防止するため、ステロイドや抗ヒスタミン薬などを併用し、治療を進めます。
フィラリア死滅による副作用を防止するため、ステロイドや抗ヒスタミン薬などを併用し、治療を進めます。
外科的治療(吊り出し法)
大量の成虫が心臓に寄生している場合におこなう治療法で、心臓につながる血管の中に細長いカテーテルを挿入し成虫を摘出します。
しかし、特殊な設備と高度な技術が求められるため対応できる動物病院が少ないという実情も。
また、麻酔やカテーテル挿入により犬の体に負担がかかるというリスクもあります。
しかし、特殊な設備と高度な技術が求められるため対応できる動物病院が少ないという実情も。
また、麻酔やカテーテル挿入により犬の体に負担がかかるというリスクもあります。
犬フィラリア症の薬はどこで購入できる?

フィラリア症の予防薬は、基本的には獣医師の処方のもと動物病院でのみ購入できるものです。ペットショップやホームセンターなどで購入することはできません。
ただし、海外ではフィラリア予防薬の市販が認められている国も多く、個人使用目的であれば、インターネット上で購入(個人輸入)が可能です。
しかし偽物の可能性があったり、安全性の保証がなかったりすることも少なくありません。そのため、予防薬を投与した後、仮に愛犬の体になにかあっても、すべて自己責任となってしまいます。
前述した通り、フィラリアの予防薬は投与する前に、感染の有無を検査する必要があります。愛犬の健康を守るためには投与前の検査も含め、獣医師から処方してもらうのが安心です。
動物病院が遠方にしかなかったり連れて行く時間がなかったりする場合は、動物病院への通院代行サービスや往診などの利用を検討してみましょう。
ただし、海外ではフィラリア予防薬の市販が認められている国も多く、個人使用目的であれば、インターネット上で購入(個人輸入)が可能です。
しかし偽物の可能性があったり、安全性の保証がなかったりすることも少なくありません。そのため、予防薬を投与した後、仮に愛犬の体になにかあっても、すべて自己責任となってしまいます。
前述した通り、フィラリアの予防薬は投与する前に、感染の有無を検査する必要があります。愛犬の健康を守るためには投与前の検査も含め、獣医師から処方してもらうのが安心です。
動物病院が遠方にしかなかったり連れて行く時間がなかったりする場合は、動物病院への通院代行サービスや往診などの利用を検討してみましょう。
獣医師に聞いた! 犬のフィラリア症のQ&A
フィラリア症にかかったら、完治しないってホント?
フィラリアに感染しても、前述した治療をおこなうことで、症状の程度によっては改善が見込まれます。
しかし、フィラリアの成虫が多数存在していて、咳をしたり、運動を嫌ったりといった慢性的な症状があると、心臓だけでなく、肺、肝臓、腎臓も障害を受けます。
治療せずに放置しておくと、呼吸が困難になる、動けなくなる、血色素尿を排出するなどの症状が出る「急性フィラリア症」を発症。短期間で死亡してしまいます。
治療したとしても、障害を受けた臓器が元通りに回復して、犬の状態がよくなるまでにはとても時間がかかります。
フィラリアを取り除いた後も、継続的に通院し、適切な治療をすることが必要です。
しかし、フィラリアの成虫が多数存在していて、咳をしたり、運動を嫌ったりといった慢性的な症状があると、心臓だけでなく、肺、肝臓、腎臓も障害を受けます。
治療せずに放置しておくと、呼吸が困難になる、動けなくなる、血色素尿を排出するなどの症状が出る「急性フィラリア症」を発症。短期間で死亡してしまいます。
治療したとしても、障害を受けた臓器が元通りに回復して、犬の状態がよくなるまでにはとても時間がかかります。
フィラリアを取り除いた後も、継続的に通院し、適切な治療をすることが必要です。
予防薬が使えない犬種はいるの?
ラフコリー、シェトランドシープドッグ、ボーダーコリーなどのコリー系の犬種は、「MDR1遺伝子」が変異しているといわれています。「イベルメクチン」を含む予防薬を投与した場合、けいれん、傾眠、運動失調のような神経症状を呈することも。一般的な予防薬に含まれる用量では副作用が出る可能性は低いとされていますが、副作用を避けるために、コリー系の犬種には「イベルメクチン」を含まないフィラリア予防薬を使用することが多いです。
獣医師からのメッセージ
犬のフィラリア症は、定期的に予防することで防ぐことができる病気です。逆に、予防していないと、感染するリスクが高くなり、わんちゃんの体に大きな負担をかけてしまい、最悪の場合死亡してしまう怖い病気です。今はいろいろなタイプの予防薬があるため、飼い主様のライフスタイルや、わんちゃんの性格や健康状態にあった予防薬を動物病院で処方してもらうとよいでしょう。きちんと予防し、わんちゃんの健康を守ってあげてくださいね!
まとめ

感染すると、死の可能性もあるほど恐ろしい犬のフィラリア症。
予防は、愛犬をフィラリアから守る飼い主の大事な責任です。予防薬のタイプはさまざまなので、飼い主のライフスタイルや愛犬の性格・体質に合わせて処方してもらいましょう。
予防は、愛犬をフィラリアから守る飼い主の大事な責任です。予防薬のタイプはさまざまなので、飼い主のライフスタイルや愛犬の性格・体質に合わせて処方してもらいましょう。